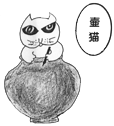文学
ストーンヘンジ
17-09-17 08:28 更新
この夏のこと、夏至の日にストーンヘンジが賑わいました。世界一有名なストーンヘンジ、イギリスのソールズベリーにある環状列石に集まった人たちが巨石群の周りで日の出を待っている、巨石のどこから太陽が昇るかという興味らしい。
イギリスのストーンヘンジの向きは北東と南西を向いて開いているそうで、これは鬼門と裏鬼門の方角にあたります。春分と秋分には、太陽は真東から昇り、真西へ沈む。洋の東西を問わず、なぜ真東真西より、北東、南西をマークするのでしょう。
大昔の人たちが何を考えて、こういうものを作ったのかと推測が続いて決定打は出ないみたいですが、これは全部棚に上げておき、自分で石を配置した経験から、環状列石や、日本にも散在する不可解な石の群れを作った人々の気持ちを考えてみようと思います。
私が作ったのは、地面に並べた石ころという単純素朴なものです。自分のために、自分が欲した配置をデザインして製作した石庭とも呼べますが、大層なスケールのものではなくて、ささやかな庭先の箱庭のようなものです。
肝心なことは、眺める庭ではないこと、使うための場所と空間であること、自分自身が本当に必要とする配置であることです。つまりストーンヘンジの解釈は、そういう心の立ち位置に立ってみて初めて見えてくるのではないでしょうか。
正方形の庭を二つ作った、まずはその一方を紹介しましょう。
正方形に区切った中央に丸石があります。これを中心として四方に石が並びます。真上から見ると十文字に見える、この方向が東西南北です。ほぼ正確に真南、真東を向いて立つことができます。周囲は隙間なく小型の丸石で埋めて、隙間には白い砕石を詰めてあります。
石は全部花崗岩なので夜も白く見えます。夜に地面が白いということは侵入者が入りにくい。目立ちますから防犯になります。さらに防犯灯を設置しているので猫一匹でもわかります。雑草は1本も生えず、地下に有孔排水管を通しているので排水が良い。
この庭は高齢者向き庭であり、草むしりや庭木の剪定から完全に解放されて心理的にも負担がゼロ、そろそろ草むしりしなくちゃ、なんて考える必要がないのです。この庭に出て歩く。姿勢を正して裸足で歩く。これが健康法です。
もう一方の正方形も紹介しましょう。
こちらの正方形は9つに分割されており、その9区画に、それぞれ丸石が配置されています。この石もまた花崗岩ですが、区画ごとに石の数が違います。まず1列目が6個、1個、8個。2列目が7、5、3。3列目が2、9、1と並びます。
そう、これは魔方陣の配置で、縦、横、斜めの石の数の合計が15になるものです。実はこの配置こそが陰陽五行思想、風水、八卦など東洋思想の根幹に位置する重要な座であり、私には欠かせない世界です。この石の周りにも白い小石が敷き詰めてあり、ここもまた運動場なのですが、一方と違う点は中央にベンチブランコが下がっていることです。
このブランコもまた自分自身のためのもので、しばしばブランコに揺れながら昼寝をし、読書をし、猫を抱いて揺れている次第。なぜブランコなのか。精神世界の中央で緩やかに揺れる座、これが胎内感覚とつながる命の根源である故です。胎内に眠る感覚から生まれる発想が私の夢類、と言いたいのですが。さてどんなものでしょうか。
昔からこんな庭であったはずもなく、四、五十代の頃は、金柑と柚子が実り、ブルーベリーがザルいっぱい採れてパイを焼き、桃ノ木まであったのですが、年齢とともに庭もまた移り変わりました。
イギリスのストーンヘンジの向きは北東と南西を向いて開いているそうで、これは鬼門と裏鬼門の方角にあたります。春分と秋分には、太陽は真東から昇り、真西へ沈む。洋の東西を問わず、なぜ真東真西より、北東、南西をマークするのでしょう。
大昔の人たちが何を考えて、こういうものを作ったのかと推測が続いて決定打は出ないみたいですが、これは全部棚に上げておき、自分で石を配置した経験から、環状列石や、日本にも散在する不可解な石の群れを作った人々の気持ちを考えてみようと思います。
私が作ったのは、地面に並べた石ころという単純素朴なものです。自分のために、自分が欲した配置をデザインして製作した石庭とも呼べますが、大層なスケールのものではなくて、ささやかな庭先の箱庭のようなものです。
肝心なことは、眺める庭ではないこと、使うための場所と空間であること、自分自身が本当に必要とする配置であることです。つまりストーンヘンジの解釈は、そういう心の立ち位置に立ってみて初めて見えてくるのではないでしょうか。
正方形の庭を二つ作った、まずはその一方を紹介しましょう。
正方形に区切った中央に丸石があります。これを中心として四方に石が並びます。真上から見ると十文字に見える、この方向が東西南北です。ほぼ正確に真南、真東を向いて立つことができます。周囲は隙間なく小型の丸石で埋めて、隙間には白い砕石を詰めてあります。
石は全部花崗岩なので夜も白く見えます。夜に地面が白いということは侵入者が入りにくい。目立ちますから防犯になります。さらに防犯灯を設置しているので猫一匹でもわかります。雑草は1本も生えず、地下に有孔排水管を通しているので排水が良い。
この庭は高齢者向き庭であり、草むしりや庭木の剪定から完全に解放されて心理的にも負担がゼロ、そろそろ草むしりしなくちゃ、なんて考える必要がないのです。この庭に出て歩く。姿勢を正して裸足で歩く。これが健康法です。
もう一方の正方形も紹介しましょう。
こちらの正方形は9つに分割されており、その9区画に、それぞれ丸石が配置されています。この石もまた花崗岩ですが、区画ごとに石の数が違います。まず1列目が6個、1個、8個。2列目が7、5、3。3列目が2、9、1と並びます。
そう、これは魔方陣の配置で、縦、横、斜めの石の数の合計が15になるものです。実はこの配置こそが陰陽五行思想、風水、八卦など東洋思想の根幹に位置する重要な座であり、私には欠かせない世界です。この石の周りにも白い小石が敷き詰めてあり、ここもまた運動場なのですが、一方と違う点は中央にベンチブランコが下がっていることです。
このブランコもまた自分自身のためのもので、しばしばブランコに揺れながら昼寝をし、読書をし、猫を抱いて揺れている次第。なぜブランコなのか。精神世界の中央で緩やかに揺れる座、これが胎内感覚とつながる命の根源である故です。胎内に眠る感覚から生まれる発想が私の夢類、と言いたいのですが。さてどんなものでしょうか。
昔からこんな庭であったはずもなく、四、五十代の頃は、金柑と柚子が実り、ブルーベリーがザルいっぱい採れてパイを焼き、桃ノ木まであったのですが、年齢とともに庭もまた移り変わりました。
真似、学ぶ
12-05-17 11:03 更新
「真似する」という言葉と「学ぶ」という言葉は、合体してもいいんじゃないか、とさえ思うことがある。
サル真似という。これは上っ面を真似することで、揶揄する響きがある。コピーキャットcopy catという。これも他人の行動、服装、考え方から何でも真似をする人のことを言う。子どもたちが真似っこをするとき、からかって使っていたが、これは英語で通用する表現で、日本では使わないのかもしれない。
ともかく、猫が人真似することを言うのだが、猿と猫の仲間に烏を入れてあげたいというのが本文の趣旨であります。
真似をすることで学習する。記憶して使う。さらに教える。サルもネコも、そしてカラスも、これをする。
私はサルと付き合ったことがないので何も言えないから言わないことにして、ネコは何匹か付き合いがあり、今も富士とマルオと付き合っているから、多少のことは言える。富士は人工的に繁殖させられたネコであった。誕生前から人の手のうちにいて清潔なタオルに包まれて育ってきた。今も室内にいて、散歩に出るときはリードをつけている。いつも私との二人暮らしであるから、ネコ同士の付き合いは自由ネコのマルオとの網戸越しに限られる。富士は、わずかの時間の網戸越しの付き合いからマルオのすることを観察して覚え、後で真似をしてみることを始めた。マルオには食後の習慣がある。満腹すると正座して、片手を使い顔を洗う。耳の後ろに手を回して鼻先までを丁寧に清掃する。左右しっかり行う。これが終わると手のひらを舐める。犬と違って手のひら返しができるので、爪の根元も綺麗に掃除する。長々と顔を洗うマルオを眺めていた富士は、ある時からマルオそっくりの仕草で顔を洗うようになった。富士は、これをしなかったのだ、長い間。知らなかったのだ、顔を洗うということを。
仲間から学ぶことがたくさんあるに違いない、富士は、顔を洗えるようにはなったが、今のままの交流態度だったら、まず猫社会には入れないだろう。社交ができない。マルオを眺めて仔細に観察し、真似はするが、近寄ってくると大口を開けて威嚇する。恐れている。付き合いの経験がないから恐怖しか抱くことができない。
幼い頃から仲間とともにいることが、どれほどの物をもたらすか驚嘆する。これは他人事ではない。
カラスとは長い付き合いをしてきた。二階のベランダに雨水を貯めている水槽がある。この水槽でカラスが水浴びをする。カラスの行水というのは、入浴時間が短いことのたとえだけれど、野生のカラスは水浴びが大好きだ。良い水場があれば毎日水浴びをする。子連れのカラスが来た時、親が水浴びをしてフェンスの柵に戻った。巣立ちをしたばかりの子ガラスは初めての水場で、柵から見下ろすばかりである。何度も何度も、親ガラスは水浴びをして見せて柵に戻る。根気よく繰り返す親ガラス。じっと見おろす子ガラス。それを物陰からじっと見つめる私。
これはヒトの時間ではないのだ、カラスの時間が流れているのだから、私にとっては痺れる長さだが、カラスはこともなげに続ける。そうして。ついに子ガラスが不器用ながらも水槽に飛び込んだ。
ヤッタァ、と喜んだのは私で、親ガラスは、生まれて初めての水浴びを味わっている子ガラスを残して晴れ晴れと飛び去っていった。
翌日からは、一緒の水浴びになった。教えたのだ、学んだのだ。
サル真似という。これは上っ面を真似することで、揶揄する響きがある。コピーキャットcopy catという。これも他人の行動、服装、考え方から何でも真似をする人のことを言う。子どもたちが真似っこをするとき、からかって使っていたが、これは英語で通用する表現で、日本では使わないのかもしれない。
ともかく、猫が人真似することを言うのだが、猿と猫の仲間に烏を入れてあげたいというのが本文の趣旨であります。
真似をすることで学習する。記憶して使う。さらに教える。サルもネコも、そしてカラスも、これをする。
私はサルと付き合ったことがないので何も言えないから言わないことにして、ネコは何匹か付き合いがあり、今も富士とマルオと付き合っているから、多少のことは言える。富士は人工的に繁殖させられたネコであった。誕生前から人の手のうちにいて清潔なタオルに包まれて育ってきた。今も室内にいて、散歩に出るときはリードをつけている。いつも私との二人暮らしであるから、ネコ同士の付き合いは自由ネコのマルオとの網戸越しに限られる。富士は、わずかの時間の網戸越しの付き合いからマルオのすることを観察して覚え、後で真似をしてみることを始めた。マルオには食後の習慣がある。満腹すると正座して、片手を使い顔を洗う。耳の後ろに手を回して鼻先までを丁寧に清掃する。左右しっかり行う。これが終わると手のひらを舐める。犬と違って手のひら返しができるので、爪の根元も綺麗に掃除する。長々と顔を洗うマルオを眺めていた富士は、ある時からマルオそっくりの仕草で顔を洗うようになった。富士は、これをしなかったのだ、長い間。知らなかったのだ、顔を洗うということを。
仲間から学ぶことがたくさんあるに違いない、富士は、顔を洗えるようにはなったが、今のままの交流態度だったら、まず猫社会には入れないだろう。社交ができない。マルオを眺めて仔細に観察し、真似はするが、近寄ってくると大口を開けて威嚇する。恐れている。付き合いの経験がないから恐怖しか抱くことができない。
幼い頃から仲間とともにいることが、どれほどの物をもたらすか驚嘆する。これは他人事ではない。
カラスとは長い付き合いをしてきた。二階のベランダに雨水を貯めている水槽がある。この水槽でカラスが水浴びをする。カラスの行水というのは、入浴時間が短いことのたとえだけれど、野生のカラスは水浴びが大好きだ。良い水場があれば毎日水浴びをする。子連れのカラスが来た時、親が水浴びをしてフェンスの柵に戻った。巣立ちをしたばかりの子ガラスは初めての水場で、柵から見下ろすばかりである。何度も何度も、親ガラスは水浴びをして見せて柵に戻る。根気よく繰り返す親ガラス。じっと見おろす子ガラス。それを物陰からじっと見つめる私。
これはヒトの時間ではないのだ、カラスの時間が流れているのだから、私にとっては痺れる長さだが、カラスはこともなげに続ける。そうして。ついに子ガラスが不器用ながらも水槽に飛び込んだ。
ヤッタァ、と喜んだのは私で、親ガラスは、生まれて初めての水浴びを味わっている子ガラスを残して晴れ晴れと飛び去っていった。
翌日からは、一緒の水浴びになった。教えたのだ、学んだのだ。
不毛の抵抗
26-03-17 11:35 更新
ノーベル文学賞を受賞したジャーナリスト、アレクシェービッチさんが福島を訪ねてくれた。去年の11月のことだったが、その日々をNHKBS1が放映してくれた。彼女の感想の中に、日本人には抵抗の文化がない、という言葉があった。
それで私は、私個人がいつ、どのように抵抗してきたかを振り返ってみて、まずはタバコの抵抗を書いたところだ。もう一つの思い出を書いてから、改めてアレクシェービッチさんの番組を見た感想を記そうと予定している。
こっちの話は、私の子供たちが大学に通っていた頃のことだ。近所で騒動があった。一家四人の家庭の夫が逮捕された事件だった。この家との付き合いはなく、顔は知っているが話したことはない。
留守宅に取材記者が押し寄せた。住宅街で、どの家も似たり寄ったりの一戸建て、猫の額の庭と車、そういう場所である。取材者は皆、機動性に富むハンターだった。奥さんは買い物に出なければ暮らせない。やむなく出るとハンターの群れが発するカメラの視線を浴びるのである。これはTVでよくみる日常風景だ。でも私は、これはしてはいけないことだと思った。許してはならぬ行為だと思い、たちまち憤激が身体を貫いたのだった。
当時私が持っていたカメラの一つにモータードライブを装着していたので、これにズームレンズをつけて道に出た。そして取材記者たちを狙って撮影を始めた。嫌がった。顔を背ける。
どう? と私は言った、どんな気持ち? 私も取材なんですよ、文芸誌「夢類」の河合です。
あの時、一声もあげることなく顔を伏せた記者たちは、この時のことを覚えているだろうか、私は引き続き憤激中だけれど。
余計なことを付け加えると、この事件は政治的な要素の強いものであり、経済界の一分野で神様と呼ばれる人物が被った災難であった。
振り返ると私は、不毛の抵抗を続けて生きてきたと思う。なぜ不毛続きかというと、団結せず、共闘せず、声をあげることもない、うちうちの抵抗だったから、なきに等しい所業である‥‥のだ。
それで私は、私個人がいつ、どのように抵抗してきたかを振り返ってみて、まずはタバコの抵抗を書いたところだ。もう一つの思い出を書いてから、改めてアレクシェービッチさんの番組を見た感想を記そうと予定している。
こっちの話は、私の子供たちが大学に通っていた頃のことだ。近所で騒動があった。一家四人の家庭の夫が逮捕された事件だった。この家との付き合いはなく、顔は知っているが話したことはない。
留守宅に取材記者が押し寄せた。住宅街で、どの家も似たり寄ったりの一戸建て、猫の額の庭と車、そういう場所である。取材者は皆、機動性に富むハンターだった。奥さんは買い物に出なければ暮らせない。やむなく出るとハンターの群れが発するカメラの視線を浴びるのである。これはTVでよくみる日常風景だ。でも私は、これはしてはいけないことだと思った。許してはならぬ行為だと思い、たちまち憤激が身体を貫いたのだった。
当時私が持っていたカメラの一つにモータードライブを装着していたので、これにズームレンズをつけて道に出た。そして取材記者たちを狙って撮影を始めた。嫌がった。顔を背ける。
どう? と私は言った、どんな気持ち? 私も取材なんですよ、文芸誌「夢類」の河合です。
あの時、一声もあげることなく顔を伏せた記者たちは、この時のことを覚えているだろうか、私は引き続き憤激中だけれど。
余計なことを付け加えると、この事件は政治的な要素の強いものであり、経済界の一分野で神様と呼ばれる人物が被った災難であった。
振り返ると私は、不毛の抵抗を続けて生きてきたと思う。なぜ不毛続きかというと、団結せず、共闘せず、声をあげることもない、うちうちの抵抗だったから、なきに等しい所業である‥‥のだ。
自分とつきあう
01-01-17 10:08 更新
壺猫 明けましておめでとうございます。
猫の目のように変わるという諺があり、状況が目まぐるしく変化するような時の例えに使われる。
実際、壺猫の目玉も、富士猫の目も、糸のように細くなったり暗闇では前開の円にかわる。人の目は不動で、眩しい時は目をほそめるだけだ。人の目は不動、そうして物事をありのままに見て事実を正確につかむことができると信じてきた。りんごはいつもりんごに見えるし、ミカンはいつもミカンに見える。
鏡を見ると自分が映る。それは長い間ほとんど毎日向き合ってきた鏡の中の私だ。鏡よ鏡、鏡さん、と鏡の中の自分に向かって声をかけたことは一度もない。わかりきっている自分自身なのだから疑念が湧くはずがない。そこには正真正銘の自分自身が映っているだけである。
今年の初めにあたり、私はこれに深い疑いを抱いた。いったい私は、今現在の、ありのままの自分を見ているのだろうか、鏡の中に。
というのは、鏡の中に見た自分と、何人かで撮った写真の中の自分の顔が、あまりにも違いすぎる。皆で撮った写真の中の、周りの人たちの顔は実物と同じに撮れている、私だけがたいそうな年寄りで、しわしわのシワだらけで、たしか以前は、もう少し丸顔だったはずなのに、やたらと垂れ下がった長顔の、みすぼらしい老女そのものだ。私って、こんなはずじゃない。ヘンだ。なんなんだ、これは。これが不満で写真を撮ってもらうのが面白くなくなった。いつから写真写りが悪くなったのかしら。
年の初めに、こんなことを思い巡らせた挙句、しぶしぶ認めたことは、私の目が事実を見ていないという現実だった。
鏡の中の私は、湯気で曇ったのか目がかすんだのか、シワひとつなく、誰にも向けたことのないような優しげな眼差しで私を見つめ返している。これは記憶の顔なのだった。願いの顔、希望の顔、と言ってもよいかもしれない。なんと私の目は、いつの間にか猫の目のようにくるくると変わり、鏡の中に往年の自分を映し出して見つめている、そういうことじゃないかと思い当たったのである。
冗談じゃない。これが自分の顔だけの問題なら失笑もので済むだろうが、他の事柄についてコレをやっていたら、と思うと緊張せざるをえないのである。例えば働き盛りの年齢になっている子供達を、少年時代に修正して見ているということ。あるいは、以前できていたことは今も出来るという肥大化した自信。今年は、このズレを修正して現実の自分自身と付き合おう。
猫の目のように変わるという諺があり、状況が目まぐるしく変化するような時の例えに使われる。
実際、壺猫の目玉も、富士猫の目も、糸のように細くなったり暗闇では前開の円にかわる。人の目は不動で、眩しい時は目をほそめるだけだ。人の目は不動、そうして物事をありのままに見て事実を正確につかむことができると信じてきた。りんごはいつもりんごに見えるし、ミカンはいつもミカンに見える。
鏡を見ると自分が映る。それは長い間ほとんど毎日向き合ってきた鏡の中の私だ。鏡よ鏡、鏡さん、と鏡の中の自分に向かって声をかけたことは一度もない。わかりきっている自分自身なのだから疑念が湧くはずがない。そこには正真正銘の自分自身が映っているだけである。
今年の初めにあたり、私はこれに深い疑いを抱いた。いったい私は、今現在の、ありのままの自分を見ているのだろうか、鏡の中に。
というのは、鏡の中に見た自分と、何人かで撮った写真の中の自分の顔が、あまりにも違いすぎる。皆で撮った写真の中の、周りの人たちの顔は実物と同じに撮れている、私だけがたいそうな年寄りで、しわしわのシワだらけで、たしか以前は、もう少し丸顔だったはずなのに、やたらと垂れ下がった長顔の、みすぼらしい老女そのものだ。私って、こんなはずじゃない。ヘンだ。なんなんだ、これは。これが不満で写真を撮ってもらうのが面白くなくなった。いつから写真写りが悪くなったのかしら。
年の初めに、こんなことを思い巡らせた挙句、しぶしぶ認めたことは、私の目が事実を見ていないという現実だった。
鏡の中の私は、湯気で曇ったのか目がかすんだのか、シワひとつなく、誰にも向けたことのないような優しげな眼差しで私を見つめ返している。これは記憶の顔なのだった。願いの顔、希望の顔、と言ってもよいかもしれない。なんと私の目は、いつの間にか猫の目のようにくるくると変わり、鏡の中に往年の自分を映し出して見つめている、そういうことじゃないかと思い当たったのである。
冗談じゃない。これが自分の顔だけの問題なら失笑もので済むだろうが、他の事柄についてコレをやっていたら、と思うと緊張せざるをえないのである。例えば働き盛りの年齢になっている子供達を、少年時代に修正して見ているということ。あるいは、以前できていたことは今も出来るという肥大化した自信。今年は、このズレを修正して現実の自分自身と付き合おう。
死の部屋
17-10-16 14:27 更新
承前
人を殺す人がいる、あらゆる時代のあらゆる社会で、無慮無数の動機で人を殺す人がいる。
殺された者の何増倍の者たちが、その死を悼み悲しみ怒り続け、殺した者に対して復讐心を抱き厳罰を望む。
ひとりの犯人を何万回殺しても、その罪は贖えぬと悶え苦しむ者を思いやる。死刑に処すことをする社会もあり、止めた国もある。
日本ではどうしたものかという論議がしばしばなされるが、万人の心を落ち着かせる姿を誰も描くことができていないのではないか。
死刑廃止論者の意見に私は、一も二もなく同意する自分を見ているが、愛する者を殺されて苦しんでいる人たちを、廃止論者がどのように救おうとするのかは、聞いたことがないし、読んだこともない。まるで被害者側は放り出されて忘れ去られる運命を甘受しなければならないとでもいうような感じを受ける。これでは廃止論者の意見が通用するはずがないと思う。
一方、手段はどうであれ、人が人を殺す行為が行われるのが死刑という刑罰だ。任務であれ、人に、このような苛酷な負担をかけてよいものだろうか、問うまでもなく悪いに決まっている。
私は宙に描いてみるのだ、刑罰として造られた死の部屋を。
それは人が作った部屋ではなく自然の洞穴だ。できることなら地球上に一つあればよい。
その洞穴には自らの意思と足で歩み入るしかない。
いかな大悪人といえども、嫌だという者は入る必要はない。では犯人は許されるのか。
とんでもないことだ、死を悼む者たちから無期限に監視され続ける環境に生きて社会奉仕を続ける。許されるのは、苦しむ者たちから、もういい、十分贖ったという声が聞こえた時だ。
私は、誰も入ったことのない死の洞穴を持つ社会にしたい、そして大罪を犯した者、被害者周辺の苦しみ続ける人々、その両方が癒されて浄化される社会を白昼夢として思い浮かべる。
付記
それにしても!
戦争を企てる政治家こそ、万死に値すると思いませんか。
人を殺す人がいる、あらゆる時代のあらゆる社会で、無慮無数の動機で人を殺す人がいる。
殺された者の何増倍の者たちが、その死を悼み悲しみ怒り続け、殺した者に対して復讐心を抱き厳罰を望む。
ひとりの犯人を何万回殺しても、その罪は贖えぬと悶え苦しむ者を思いやる。死刑に処すことをする社会もあり、止めた国もある。
日本ではどうしたものかという論議がしばしばなされるが、万人の心を落ち着かせる姿を誰も描くことができていないのではないか。
死刑廃止論者の意見に私は、一も二もなく同意する自分を見ているが、愛する者を殺されて苦しんでいる人たちを、廃止論者がどのように救おうとするのかは、聞いたことがないし、読んだこともない。まるで被害者側は放り出されて忘れ去られる運命を甘受しなければならないとでもいうような感じを受ける。これでは廃止論者の意見が通用するはずがないと思う。
一方、手段はどうであれ、人が人を殺す行為が行われるのが死刑という刑罰だ。任務であれ、人に、このような苛酷な負担をかけてよいものだろうか、問うまでもなく悪いに決まっている。
私は宙に描いてみるのだ、刑罰として造られた死の部屋を。
それは人が作った部屋ではなく自然の洞穴だ。できることなら地球上に一つあればよい。
その洞穴には自らの意思と足で歩み入るしかない。
いかな大悪人といえども、嫌だという者は入る必要はない。では犯人は許されるのか。
とんでもないことだ、死を悼む者たちから無期限に監視され続ける環境に生きて社会奉仕を続ける。許されるのは、苦しむ者たちから、もういい、十分贖ったという声が聞こえた時だ。
私は、誰も入ったことのない死の洞穴を持つ社会にしたい、そして大罪を犯した者、被害者周辺の苦しみ続ける人々、その両方が癒されて浄化される社会を白昼夢として思い浮かべる。
付記
それにしても!
戦争を企てる政治家こそ、万死に値すると思いませんか。
選挙戦について
16-10-16 11:45 更新
先だっての都知事選のとき、対立候補の女性関係に関する噂を蒸し返した週刊誌の記事が出て、戦いの刃とされた。今、対岸の国の大統領選でも、昔のセクハラなどを持ち出して非難合戦をしている。
これが政治なのよ。対立候補が、そう言った。
これが大衆なのよ、と私には聞こえた。風評だろうが噂だろうが、テレビで放映され、週刊誌が書く、これで簡単に左右されてしまうのだ。特に女性問題が槍玉に挙げられると、事実か嘘かは棚上げされて、問答無用で選挙に不利になってしまう。
つまり、過去に悪いことをすると、次に良いことをしようと進もうとした場合に、蒸し返されて進路を阻まれるのだ。私は、この選挙戦を見物しながら、このことを考えた。
誤ったことをしてしまった過去を持つ人に将来はないのだろうか。悔い改めたら、第二の人生を進む道路は用意されないのだろうか。希望はないのだろうか。
これは良くないと思う。誰であれ、最後まで希望は手放してはいけないし、希望を取り上げてはいけない。
よく、喩えとして、蓋をしていた悪事が噴出することを「パンドラの箱を開けてしまった」と言われるが、本当の喩えとしてパンドラの箱は「最後に箱の底に残っていたのは希望だった」という、ここをこそ、喩えとして使って欲しいと思うのだ。続く
これが政治なのよ。対立候補が、そう言った。
これが大衆なのよ、と私には聞こえた。風評だろうが噂だろうが、テレビで放映され、週刊誌が書く、これで簡単に左右されてしまうのだ。特に女性問題が槍玉に挙げられると、事実か嘘かは棚上げされて、問答無用で選挙に不利になってしまう。
つまり、過去に悪いことをすると、次に良いことをしようと進もうとした場合に、蒸し返されて進路を阻まれるのだ。私は、この選挙戦を見物しながら、このことを考えた。
誤ったことをしてしまった過去を持つ人に将来はないのだろうか。悔い改めたら、第二の人生を進む道路は用意されないのだろうか。希望はないのだろうか。
これは良くないと思う。誰であれ、最後まで希望は手放してはいけないし、希望を取り上げてはいけない。
よく、喩えとして、蓋をしていた悪事が噴出することを「パンドラの箱を開けてしまった」と言われるが、本当の喩えとしてパンドラの箱は「最後に箱の底に残っていたのは希望だった」という、ここをこそ、喩えとして使って欲しいと思うのだ。続く
平櫛田中彫刻美術館
02-10-16 15:08 更新
平櫛田中という彫刻家について、伝え聞いたエピソードがあります。それは、高齢になってから、この先彫刻するための木材を庭先で乾燥させていた、乾燥するには何年もかかるというのに、高齢になってからやっていた、という話です。人間の生き方の根本に触れる行為なので、時々思い出します。
時の拍子で、小平市に美術館があると知り、知ってしまったら落ち着かなくなり、秋雨の合間に傘を持ち、さしたり杖に突いたりを繰り返しつつ出かけました。
はじめ、小平市平櫛田中館として旧宅を公開したのち展示館を新築し、今は2館併設の形になっています。
私が気にしている彫刻用材は、直径2、30センチのものと想像していたし、すでにエピソードだけで形はないであろうと思い込んでいたのですが、ビックリ仰天、大外れ。あったのです。
それは、3人がかりで囲んでも足りないほどの太さの楠の巨木で、書院造りの旧居宅の庭先に置いてありました。
台石の上に直立させて、上を屋根で覆ってあり、それはまるで編傘を被った巨人でした。
当館の内容については非常に良くできたホームページがあり、写真も豊富に出ていますので、ぜひご覧ください。
当地に書院造りの居宅を建てて移り住んだのが98歳の時のことだそうで、100歳の時に20年後の制作のために九州から原木を取り寄せたと、説明を読んで知りました。
時を知り、それを計ることのできる人間であることを自覚しながら、志を大きく高く、長く持ち続けて、しかも実行しながら107歳を生きとおした偉人であります。と、同時に私は、ヒト以外の動物たち、季節を知るも時を知らぬと思える動物たちと同じ「時の世界」に生きていた人だったのではないかと思いめぐらせました。
もう一つ、建築について。
展示館が実に居心地が良い。飽きない。めぐる楽しさ。
あまり良いので受付の方に感想を伝えたところ、設計者について教えていただきました。
居宅は大江宏、展示館は、その息子さんの大江新。大江宏は、国立能楽堂などを設計された方です、とのこと。親子の仕事でした。いやもう、両方とも素晴らしいので、ひっくり返りそうに感動しました。こんな親子いいなあ。一緒に仕事をしたのではなくて、時の縦軸でつながり、同じ場所にいるのです。祖父から三代の連結です。
豊かな気持ちで帰る途中、この大江宏さんて、父が、建築の大江先生、といつも話題にしていた、あの大江先生のことじゃないの、と気がついて悔しいのなんの、もっと父と話をしたかったと、思いもよらぬ慚愧の涙でした。
時の拍子で、小平市に美術館があると知り、知ってしまったら落ち着かなくなり、秋雨の合間に傘を持ち、さしたり杖に突いたりを繰り返しつつ出かけました。
はじめ、小平市平櫛田中館として旧宅を公開したのち展示館を新築し、今は2館併設の形になっています。
私が気にしている彫刻用材は、直径2、30センチのものと想像していたし、すでにエピソードだけで形はないであろうと思い込んでいたのですが、ビックリ仰天、大外れ。あったのです。
それは、3人がかりで囲んでも足りないほどの太さの楠の巨木で、書院造りの旧居宅の庭先に置いてありました。
台石の上に直立させて、上を屋根で覆ってあり、それはまるで編傘を被った巨人でした。
当館の内容については非常に良くできたホームページがあり、写真も豊富に出ていますので、ぜひご覧ください。
当地に書院造りの居宅を建てて移り住んだのが98歳の時のことだそうで、100歳の時に20年後の制作のために九州から原木を取り寄せたと、説明を読んで知りました。
時を知り、それを計ることのできる人間であることを自覚しながら、志を大きく高く、長く持ち続けて、しかも実行しながら107歳を生きとおした偉人であります。と、同時に私は、ヒト以外の動物たち、季節を知るも時を知らぬと思える動物たちと同じ「時の世界」に生きていた人だったのではないかと思いめぐらせました。
もう一つ、建築について。
展示館が実に居心地が良い。飽きない。めぐる楽しさ。
あまり良いので受付の方に感想を伝えたところ、設計者について教えていただきました。
居宅は大江宏、展示館は、その息子さんの大江新。大江宏は、国立能楽堂などを設計された方です、とのこと。親子の仕事でした。いやもう、両方とも素晴らしいので、ひっくり返りそうに感動しました。こんな親子いいなあ。一緒に仕事をしたのではなくて、時の縦軸でつながり、同じ場所にいるのです。祖父から三代の連結です。
豊かな気持ちで帰る途中、この大江宏さんて、父が、建築の大江先生、といつも話題にしていた、あの大江先生のことじゃないの、と気がついて悔しいのなんの、もっと父と話をしたかったと、思いもよらぬ慚愧の涙でした。
批評の達人
21-09-16 08:29 更新
秋台風最中の世迷いごとですが。
ノーベル文学賞受賞作家の川端康成さんは『雪国』をはじめ数多の作品があり、小説家として認められているのだと思っています。重ねて、世迷い事ですと前置きをしますが、彼の小説はフツーだと、私は思う。
『雪国』を、日本小説の中で20世紀第一の名作と評価する人がいること、彼が『雪国』を、どれほどの長期間にわたり彫琢し続けていらしたかも仄聞しています。
それでも川端康成さんは、評論の方が優れている、評論家と呼ばれないかもしれないけれど、際立った、ゾッとする眼力で刺し通す、そういう評論をなさった方だと思います。
小説作品に対する眼だけではない、眼に入ったもの全てを「見て」しまう。見えてしまって、どうしようもなかったのではないか。だって見えるんだ。多分、そうおっしゃるのではないかと想像します。
私は川端康成さんの「眼」と、それを言葉に置く姿勢を、この上なく良いものと感じて尊重しています。彼の眼は自分自身の肉体、目玉以外の我を忘れきったところで、モノと対峙している。無の境地と表現するかもしれません、宗教家でしたら。私が感じているのは、全く私心がない、純粋な眼だということです。
ですから骨董も見ることができていたのでしょう。
人物評となると、けっして力んで書いているのではない、しかし私は震え上がるのです。とてもここまで見ようとしても見えるものではないが、本当だ、この通りだ、と感じ入ります。
川端康成さんは、あるとき自分自身を見たのでしょう、と思います。
世迷い事の付録。
彼の奥さんについては、名前も知らないのですが、ひとつだけ、これは本当の事だろうと思いつつ読んだ資料があります。
それは、奥さんも「見える人」であった事です。「でもわたし、見えてしまうのですもの」と、おっしゃっているような感じを持ちました。見える同士の結婚、だったのだと感じます。
ただ奥さんの方は、異世界が見える人であったので、三島由紀夫に続いて夫が自殺したとき、無責任な誰彼が、三島さんが(あの世へ)誘ったのではないか、と噂をしたときには、きっぱりと、それは違います、と答えられたそうです。そして、あの人を連れて行ったのは……、と続けられたそうですが、これ以上は当ブログの範囲外ですから、ここで止めておきます。
ノーベル文学賞受賞作家の川端康成さんは『雪国』をはじめ数多の作品があり、小説家として認められているのだと思っています。重ねて、世迷い事ですと前置きをしますが、彼の小説はフツーだと、私は思う。
『雪国』を、日本小説の中で20世紀第一の名作と評価する人がいること、彼が『雪国』を、どれほどの長期間にわたり彫琢し続けていらしたかも仄聞しています。
それでも川端康成さんは、評論の方が優れている、評論家と呼ばれないかもしれないけれど、際立った、ゾッとする眼力で刺し通す、そういう評論をなさった方だと思います。
小説作品に対する眼だけではない、眼に入ったもの全てを「見て」しまう。見えてしまって、どうしようもなかったのではないか。だって見えるんだ。多分、そうおっしゃるのではないかと想像します。
私は川端康成さんの「眼」と、それを言葉に置く姿勢を、この上なく良いものと感じて尊重しています。彼の眼は自分自身の肉体、目玉以外の我を忘れきったところで、モノと対峙している。無の境地と表現するかもしれません、宗教家でしたら。私が感じているのは、全く私心がない、純粋な眼だということです。
ですから骨董も見ることができていたのでしょう。
人物評となると、けっして力んで書いているのではない、しかし私は震え上がるのです。とてもここまで見ようとしても見えるものではないが、本当だ、この通りだ、と感じ入ります。
川端康成さんは、あるとき自分自身を見たのでしょう、と思います。
世迷い事の付録。
彼の奥さんについては、名前も知らないのですが、ひとつだけ、これは本当の事だろうと思いつつ読んだ資料があります。
それは、奥さんも「見える人」であった事です。「でもわたし、見えてしまうのですもの」と、おっしゃっているような感じを持ちました。見える同士の結婚、だったのだと感じます。
ただ奥さんの方は、異世界が見える人であったので、三島由紀夫に続いて夫が自殺したとき、無責任な誰彼が、三島さんが(あの世へ)誘ったのではないか、と噂をしたときには、きっぱりと、それは違います、と答えられたそうです。そして、あの人を連れて行ったのは……、と続けられたそうですが、これ以上は当ブログの範囲外ですから、ここで止めておきます。
手ぶらで、帰れない
11-09-16 09:12 更新
卓球の愛ちゃん。あの、よちよち歩きのチビちゃんの時から頑張ってきた福原愛選手が、今回のオリンピックで銅メダル、続いて結婚という幸せな時を迎えた。よかったねえ、おめでとう、とテレビに向かってお祝い。
取材に応えて、ホッとした、を繰り返している愛ちゃん。嬉しかった、の言葉が出ない。
手ぶらで帰さない。こんな言葉を聞いたのは、以前の水泳のときだったが、愛ちゃんの後輩選手も、同じ言葉を使い、試合前の意気込みを語っていた。海外の試合から帰国するときの空港での手ぶらの辛さを聞き、胸が痛んだ。
バカなことを思うもんじゃない、一所懸命にやった、それで十分でしょう、と声をかけたくなるのは、家庭であれば年寄りの役目かもしれない。しかし昨今、意気込みを通り越して重圧に変わってきていないか、案じられてならない。
1964年、東京オリンピックの時の男子マラソンで銅メダルを受賞した円谷幸吉選手を思う。日本人でメダルを手にしたのは、円谷選手ただ一人だったのだ。彼は、4年後には、もっと頑張りますと決意を語ったが、日本全国の、想像を超える重圧を受けて圧死した。この時の、言いようのない衝撃と悲しみが、今も胸を刳る。
リオのオリンピック前にも、メダルを取る、頑張ります、の決意が各所で語られた。メディアは、メダルの数を予想し、数える。そんなところにオリンピックの精神があるのだろうか。四年後には、たぶん東京オリンピックが開催されることだろう。そこまで生きているかどうかわからないが、一人でも多くの人が、バカなことを思うもんじゃない、と言って欲しいと願っている。
取材に応えて、ホッとした、を繰り返している愛ちゃん。嬉しかった、の言葉が出ない。
手ぶらで帰さない。こんな言葉を聞いたのは、以前の水泳のときだったが、愛ちゃんの後輩選手も、同じ言葉を使い、試合前の意気込みを語っていた。海外の試合から帰国するときの空港での手ぶらの辛さを聞き、胸が痛んだ。
バカなことを思うもんじゃない、一所懸命にやった、それで十分でしょう、と声をかけたくなるのは、家庭であれば年寄りの役目かもしれない。しかし昨今、意気込みを通り越して重圧に変わってきていないか、案じられてならない。
1964年、東京オリンピックの時の男子マラソンで銅メダルを受賞した円谷幸吉選手を思う。日本人でメダルを手にしたのは、円谷選手ただ一人だったのだ。彼は、4年後には、もっと頑張りますと決意を語ったが、日本全国の、想像を超える重圧を受けて圧死した。この時の、言いようのない衝撃と悲しみが、今も胸を刳る。
リオのオリンピック前にも、メダルを取る、頑張ります、の決意が各所で語られた。メディアは、メダルの数を予想し、数える。そんなところにオリンピックの精神があるのだろうか。四年後には、たぶん東京オリンピックが開催されることだろう。そこまで生きているかどうかわからないが、一人でも多くの人が、バカなことを思うもんじゃない、と言って欲しいと願っている。
天皇・すめろぎ・すめらみこと
16-08-16 13:16 更新
三島由紀夫が「などて天皇は人間(ひと)となりたまひし」と書いた、これを「すめらみこと」と覚えていたが、調べてみると「すめろぎ」と出ている。これは両方とも天皇を意味するが、「すめろぎ」は一般的な天皇の意、「すめらみこと」は今上天皇を指すと思っていた。実際、三島由紀夫は、昭和天皇に向けて発した言葉であろうと思うので、やはり「すめらみこと」の方がしっくりするのではないか。
今回、今上天皇の「お気持ち」なる言葉を聴いている最中に、突然、三島が書いたこの言葉が湧き上がってきた。この瞬間まで私は、三島由紀夫って、何言ってんのよと思っていたのだ、いろいろな意味合いで。二・二六事件に入れ込み、昔を今になすよしもがな、の気分なんでしょ、と揶揄してもいた。
私の天皇観は、小誌「夢類」の読者はご存知と思うが、ひとことで言えば、象徴削除。皇室消滅不問。博物館的存在として大切にしましょう、というものである。理由は、自立型日本人の成長にある。
しかし今回私は、天皇の思うところを聴き、その思考ルートを辿りつつ、仰け反る思いで呟いた、「などてすめらみことは神となりたまはずや」。
私が国文科で学んでいた時の主任教授岩田九郎先生は、中等科時代の三島由紀夫に国語を教えていらした。三島由紀夫が世に出てからも、岩田先生は教え子を見守り続けていらした。立ち話だったと思うが、三島が『金閣寺』を発表した時に岩田先生は、(彼は)まだ、まだまだですね。とおっしゃった。どういうものか私は、敬愛する師との思い出が「立ち話」のシーンが多い。そして教室で学んだことよりも強く心に刻まれている。先生は遠くを見る目をしていらした。三島由紀夫の父君とも交流のあった先生だ。栴檀の薫りを放つ教え子が若木の内に込めていた精髄を、誰よりもご存知でいらしただろう。
はたしていま岩田先生が、明仁殿下が今上天皇となられてお言葉を発せられるご様子をご覧になられたとしたら、なんとおっしゃるであろうと思い、そして私は、いま思うところを師に訴え語りたいのである。もしも事、極まった場合、天皇と三種の神器の、どちらを救いますか? との問いに対し、三島由紀夫と同じように私は、迷わず三種の神器を守りますと、語りたいのである。
今回、今上天皇の「お気持ち」なる言葉を聴いている最中に、突然、三島が書いたこの言葉が湧き上がってきた。この瞬間まで私は、三島由紀夫って、何言ってんのよと思っていたのだ、いろいろな意味合いで。二・二六事件に入れ込み、昔を今になすよしもがな、の気分なんでしょ、と揶揄してもいた。
私の天皇観は、小誌「夢類」の読者はご存知と思うが、ひとことで言えば、象徴削除。皇室消滅不問。博物館的存在として大切にしましょう、というものである。理由は、自立型日本人の成長にある。
しかし今回私は、天皇の思うところを聴き、その思考ルートを辿りつつ、仰け反る思いで呟いた、「などてすめらみことは神となりたまはずや」。
私が国文科で学んでいた時の主任教授岩田九郎先生は、中等科時代の三島由紀夫に国語を教えていらした。三島由紀夫が世に出てからも、岩田先生は教え子を見守り続けていらした。立ち話だったと思うが、三島が『金閣寺』を発表した時に岩田先生は、(彼は)まだ、まだまだですね。とおっしゃった。どういうものか私は、敬愛する師との思い出が「立ち話」のシーンが多い。そして教室で学んだことよりも強く心に刻まれている。先生は遠くを見る目をしていらした。三島由紀夫の父君とも交流のあった先生だ。栴檀の薫りを放つ教え子が若木の内に込めていた精髄を、誰よりもご存知でいらしただろう。
はたしていま岩田先生が、明仁殿下が今上天皇となられてお言葉を発せられるご様子をご覧になられたとしたら、なんとおっしゃるであろうと思い、そして私は、いま思うところを師に訴え語りたいのである。もしも事、極まった場合、天皇と三種の神器の、どちらを救いますか? との問いに対し、三島由紀夫と同じように私は、迷わず三種の神器を守りますと、語りたいのである。
貧乏と貧乏人
20-06-16 15:18 更新
熊谷守一の随筆を手元に置いている。山頭火は、全集をひとまとめにして読了したところなので、この方の片々がまなかいに漂っている。女性では森鴎外のお嬢さんの森茉莉を思い出す。この三人を並べて絵にしたら、貧乏群像画になるかもしれない。
しかし熊谷守一は、事業家で地主の、裕福な家庭の生まれ、山頭火は、大地主、種田家の長男、森茉莉は、鴎外の愛娘。シモキタの三婆の一婆として安アパートの廊下の突き当たりにある共同水道の流しで、ほうれん草を洗って食べていたマリー。
この種族は、どれほど貧乏しても「貧乏人」にはなれない。恬淡とし、堂々とし、高貴で誇り高く、基本の礼節を肌身として生きている。
今時代のメディアに出るような人物を引き合いに出してみると、たとえば鳩山由紀夫さん。褒める人あり貶す人ありの人物だが、こんな陰口も聞こえる、「あんなに金持ちなのに細かいんだ」。これは鳩山さんが裕福な家庭に育った、それも良い育て方をして貰ったことの証しだろうと私は推測している。
地下足袋の底のゴムの製造販売をしていた鳩山家は、時代が移り、地下足袋が売れなくなった。切羽詰まって自動車のタイヤに目を向けて転向した。結果が良かったから今があるわけで、知恵を絞って働いて手に入れたお金であるからこそ、節約を重んじ、無駄をしない態度が身についている。本当の意味のお金持ちといえる。
大金持ちなんだから、もっとバラまいてもいいじゃないか、誰彼に景気よくおごってもいいじゃないかと感じる人は、金持ちの日常を知らない「貧乏人」という人種だ。貧乏人ほど、日常生活で無駄をし、物を粗雑に扱うのである。
山頭火は、山道を独り歩いた、日本の山中は清冽な水の宝庫そのもの。飲み歩く。里に下りて宿に泊まる。宿の誰かが水道の水を出しっ放しにして雑用をしているのをみて、本気で立腹している。勿体ない、彼奴はダメだ、と書いている。
先頃、都知事の席を追われた人は、「二流のビジネスホテルに泊まれますか。恥ずかしいでしょう」と言った。この時の顔つきをまじまじと見たが、心の底から、そう思っているように感じて驚いた。この人は、ほんとうの「貧乏人」なのだった。贅沢な暮らしをしていても、土台が貧乏人であると抜け出せるものではない。
だいたい、貧乏人は物事をお金で解決しようとする。心の問題までも、お金で購おうとするのである。お金の価値を限定的にとらえている相手は、心底の謝罪を欲しているときにお金を出されると激怒するものである。貧乏人には、これがわからない。
しかしまぁ、これを言ったら世の中オシマイですね。だって見てみて欲しい。買、売、購、財、貨、貸、貰、資、賜、賭、贈、贅、贋、賞、賊……、みんな貝がついているではないか。貝殻をお金として使っていた大昔から誰もが承知している99対1の人間模様だ。
しかし熊谷守一は、事業家で地主の、裕福な家庭の生まれ、山頭火は、大地主、種田家の長男、森茉莉は、鴎外の愛娘。シモキタの三婆の一婆として安アパートの廊下の突き当たりにある共同水道の流しで、ほうれん草を洗って食べていたマリー。
この種族は、どれほど貧乏しても「貧乏人」にはなれない。恬淡とし、堂々とし、高貴で誇り高く、基本の礼節を肌身として生きている。
今時代のメディアに出るような人物を引き合いに出してみると、たとえば鳩山由紀夫さん。褒める人あり貶す人ありの人物だが、こんな陰口も聞こえる、「あんなに金持ちなのに細かいんだ」。これは鳩山さんが裕福な家庭に育った、それも良い育て方をして貰ったことの証しだろうと私は推測している。
地下足袋の底のゴムの製造販売をしていた鳩山家は、時代が移り、地下足袋が売れなくなった。切羽詰まって自動車のタイヤに目を向けて転向した。結果が良かったから今があるわけで、知恵を絞って働いて手に入れたお金であるからこそ、節約を重んじ、無駄をしない態度が身についている。本当の意味のお金持ちといえる。
大金持ちなんだから、もっとバラまいてもいいじゃないか、誰彼に景気よくおごってもいいじゃないかと感じる人は、金持ちの日常を知らない「貧乏人」という人種だ。貧乏人ほど、日常生活で無駄をし、物を粗雑に扱うのである。
山頭火は、山道を独り歩いた、日本の山中は清冽な水の宝庫そのもの。飲み歩く。里に下りて宿に泊まる。宿の誰かが水道の水を出しっ放しにして雑用をしているのをみて、本気で立腹している。勿体ない、彼奴はダメだ、と書いている。
先頃、都知事の席を追われた人は、「二流のビジネスホテルに泊まれますか。恥ずかしいでしょう」と言った。この時の顔つきをまじまじと見たが、心の底から、そう思っているように感じて驚いた。この人は、ほんとうの「貧乏人」なのだった。贅沢な暮らしをしていても、土台が貧乏人であると抜け出せるものではない。
だいたい、貧乏人は物事をお金で解決しようとする。心の問題までも、お金で購おうとするのである。お金の価値を限定的にとらえている相手は、心底の謝罪を欲しているときにお金を出されると激怒するものである。貧乏人には、これがわからない。
しかしまぁ、これを言ったら世の中オシマイですね。だって見てみて欲しい。買、売、購、財、貨、貸、貰、資、賜、賭、贈、贅、贋、賞、賊……、みんな貝がついているではないか。貝殻をお金として使っていた大昔から誰もが承知している99対1の人間模様だ。
ドローン幻想
17-03-16 22:01 更新
ドローンという電動竹とんぼのようなものが現れて、あっというまに機種も揃ってきた。撮影ばかりではない、配達にも使えるという。用途は限りなく増え、機種も発達中だ。
ドローンができたとき、私は、その言葉の印象から、忍者が印を結んでドローンと消える様を想像した。実はドロンと消えるのではなくて、ドローンと飛ぶのだった。いまでも忍者の印象が続いていて、この器械が大きな荷物を運ぶ方向に進化する一方、極小化することを夢見ている。1円玉より小さいドローン。日本人は小型化するのが上手だから、もっと小さく出来るのではないかしら。
1円玉より小さい、小蝿くらいの小さなドローンが開発されたら、忍びの者は、これを子分に使い、どこにだって侵入できる。この微小ドローンは、デジタル信号を忍者に送信する。受信した側で言語化したり映像化したり、思いのままに操作できるのだ。こうなったら天井の隙間から密談中の悪代官を覗かなくても大丈夫、囁き声だってキャッチする。
忍者とは違うが、幻術を使う者がでてくる活劇では、本人が一匹のアブに変身して敵陣へ入り込む物語もあった。これこそ昔のドローンである。ドローンが益々進化して、忍者ドローン、幻術使いドローンが出来るのを楽しみにしている。
ドローンができたとき、私は、その言葉の印象から、忍者が印を結んでドローンと消える様を想像した。実はドロンと消えるのではなくて、ドローンと飛ぶのだった。いまでも忍者の印象が続いていて、この器械が大きな荷物を運ぶ方向に進化する一方、極小化することを夢見ている。1円玉より小さいドローン。日本人は小型化するのが上手だから、もっと小さく出来るのではないかしら。
1円玉より小さい、小蝿くらいの小さなドローンが開発されたら、忍びの者は、これを子分に使い、どこにだって侵入できる。この微小ドローンは、デジタル信号を忍者に送信する。受信した側で言語化したり映像化したり、思いのままに操作できるのだ。こうなったら天井の隙間から密談中の悪代官を覗かなくても大丈夫、囁き声だってキャッチする。
忍者とは違うが、幻術を使う者がでてくる活劇では、本人が一匹のアブに変身して敵陣へ入り込む物語もあった。これこそ昔のドローンである。ドローンが益々進化して、忍者ドローン、幻術使いドローンが出来るのを楽しみにしている。
歌と踊り
06-01-16 09:56 更新
歌と踊りは人間の営みの根源と思う。岩戸の前で踊るウズメ。ジャマイカでは市井の人々が毎晩のようにダンスを楽しんでいるが、ついこの間までの歌と踊りは奴隷化された人たちの命綱だった。昔、ニューヨークに住んでいたときは、隣家が毎週末にダンスパーティだった。歌が魂を慰め、踊りが命を庇う。私はジャマイカで、足が使えなくても踊れることを知り、声が上手く出なくても歌えることを学んだ。言葉が生まれる以前の人類から受け継いできた拍動と旋律は、いまもすべての人の肉体に宿るのだ。
昨年末に加島祥造さんが亡くなられた。「荒地」の詩人。亡くなられたが彼の詩句は生きている。手元にあるフォークナーの『八月の光』の訳が加島祥造さん。おなじ「荒地」の田村隆一さんの訳本も、彼の詩集と共に書架にある。詩人の訳したものは、小説であれ童話であれ日本語が美しい。小説を書く人でも、詩から入った人の言葉には愛情が籠もっている。言葉に対する敬意と愛が伝わってくる。そして思うのだが詩人はいつも心が踊っている故に、しかも時空を超える術を体得している故に、無限大の言葉のダンスに興じることができるのだ。このような詩人たちの言葉に添うて生きる私は幸せだ。
年末年始にかけて、カウントダウンのバレエ、シルヴィ・ギエムの「ボレロ」をTVで観た。バレエに詳しい友人から教えて貰って観たのだが、深紅の円盤の上で踊る女性は、ウズメと自然に重なった。身体一杯の感動だった。ウズメはギエムのように面(おもて)を上げて堂々としていただろうと思った。
昨年末に加島祥造さんが亡くなられた。「荒地」の詩人。亡くなられたが彼の詩句は生きている。手元にあるフォークナーの『八月の光』の訳が加島祥造さん。おなじ「荒地」の田村隆一さんの訳本も、彼の詩集と共に書架にある。詩人の訳したものは、小説であれ童話であれ日本語が美しい。小説を書く人でも、詩から入った人の言葉には愛情が籠もっている。言葉に対する敬意と愛が伝わってくる。そして思うのだが詩人はいつも心が踊っている故に、しかも時空を超える術を体得している故に、無限大の言葉のダンスに興じることができるのだ。このような詩人たちの言葉に添うて生きる私は幸せだ。
年末年始にかけて、カウントダウンのバレエ、シルヴィ・ギエムの「ボレロ」をTVで観た。バレエに詳しい友人から教えて貰って観たのだが、深紅の円盤の上で踊る女性は、ウズメと自然に重なった。身体一杯の感動だった。ウズメはギエムのように面(おもて)を上げて堂々としていただろうと思った。
時を知る
25-03-15 20:31 更新
人と他の生き物との違いは、人が時の流れを知る点だ。動物は季節は知っている、渡りの時、繁殖の季節など。季と時はちがう。人が人に殺意を抱き、殺しもすることができるのは「時の流れ」を知ったからだ。人を殺すということは、その人の「時」を停めること、その人の未来の「時」を殺すことだ。
人以外の動物には、同胞を殺さないDNAが備わっいるという。生きるために動物を食べる必要のある肉食動物には、肉食の本能と並んで、殺しを抑制する本能が備わっているという。ゆえに、必要以上の殺戮をしないのだという。人間には、必要以上の殺しを抑制する本能が備わっていないという。いうなれば欠落している。人間は、不完全な生き物なのだと学者は説く。
なる程、そういうものか、と納得するけれども、それに加えて、人が、人に対して「生かしちゃ、おけない」という強烈な想念を噴出させるとき、その底には、「他者の持つ時を殺したい」という欲望が渦巻いているのではないか。これでは、一人殺して満足できるはずもない。際限ない殺戮へなだれ込む原因の一つに「時」がありはしないか。
一方、「時」を知る故に、長生きを望むこともする。自分が死んだ後のことまで、計画したりする者もいる。個人の寿命を越えた世界を思い、放射能について心配する。
いま現在の「時」を越えて、さらに遙か遠い時へも思いを馳せることができるのが人間だと思う。「時」を知る能力をもらった人間、自分の役職の任期を越え、自分の寿命を越え、子々孫々の、その先までも思いを馳せることができる能力を、有意義に用いたい。目先の利害を超越して、原発の将来を想像して欲しい。
最近は、日本人衰退から消滅へ。地球人類の終焉が見えてきた、それは「核」を弄んだ故だ、という言説を耳にするようになってきた。これらの悲観的な展望を否定できない現在である。しかし人は、よい時を作り出せる力を持っているはずだ。いまは春、あっちでも、こっちでも、よい時の種を蒔きたい。
人以外の動物には、同胞を殺さないDNAが備わっいるという。生きるために動物を食べる必要のある肉食動物には、肉食の本能と並んで、殺しを抑制する本能が備わっているという。ゆえに、必要以上の殺戮をしないのだという。人間には、必要以上の殺しを抑制する本能が備わっていないという。いうなれば欠落している。人間は、不完全な生き物なのだと学者は説く。
なる程、そういうものか、と納得するけれども、それに加えて、人が、人に対して「生かしちゃ、おけない」という強烈な想念を噴出させるとき、その底には、「他者の持つ時を殺したい」という欲望が渦巻いているのではないか。これでは、一人殺して満足できるはずもない。際限ない殺戮へなだれ込む原因の一つに「時」がありはしないか。
一方、「時」を知る故に、長生きを望むこともする。自分が死んだ後のことまで、計画したりする者もいる。個人の寿命を越えた世界を思い、放射能について心配する。
いま現在の「時」を越えて、さらに遙か遠い時へも思いを馳せることができるのが人間だと思う。「時」を知る能力をもらった人間、自分の役職の任期を越え、自分の寿命を越え、子々孫々の、その先までも思いを馳せることができる能力を、有意義に用いたい。目先の利害を超越して、原発の将来を想像して欲しい。
最近は、日本人衰退から消滅へ。地球人類の終焉が見えてきた、それは「核」を弄んだ故だ、という言説を耳にするようになってきた。これらの悲観的な展望を否定できない現在である。しかし人は、よい時を作り出せる力を持っているはずだ。いまは春、あっちでも、こっちでも、よい時の種を蒔きたい。
旧市街
08-03-15 22:08 更新
久しぶりに東京、町田の旧市街を歩いた。来る度に店が入れ替わり、個人経営の店が消えて企業のチェーン店が増えてゆく。入れ替わりがうまくいっているのだろう、混雑していて、いつ行っても高校生くらいの子が道一杯に歩いている。歩道も車道も区別がない道、真ん中を這うように車が通る。好きな通りだ。
マメと雑穀を売る店でマメを買った。小鳥用のヒマワリの種なども売っている店。近くにウナギの寝床がある。この道路と平行する道をつなぐ横筋の細道のことで、入り口は雑貨屋、なかはラーメン屋、飲み屋、古着屋、佃煮屋、惣菜屋、八百屋、魚屋、豆腐屋もある。魚屋は真っ赤に染めたタラコ、タコを並べている。昭和の味がしそうだ。インドの雑貨小物を売る店、骸骨なんかがついているブレスなどを並べる店もある。昼飯屋もあるが、こうした食べさせる店は、せいぜいがスツール3つ程度のカウンターの店。シモキタの昔と似ている。見慣れない店があった。垂れ布の隙間から、小机を挟んで向き合う女性ふたりがみえた。こちらを向いているのが占い師で、背が見えるのが客らしい。10分千円と看板が立てかけてあった。スパゲティを茹でる時間が、私の場合12分だから、ゆであがる前に終わりだ。私は貧乏性だから、時間が気になって上の空になりそう。町の占いでは学割が効く店は知っているけれど、これは初めてだった。
別建ての話に逸れて恐縮ですが、占い師と客の関係は興味深い。客が問う。それに答える占い師。インタビューも同じ事だけれど、一見、答える側が内蔵する、所有する、我が身の一部を取りだして、相手に渡す形である。私が思うに、それは表面上のことであり、問う者のほうが自身をさらけ出してしまうものなのだ。これは一対一の真剣勝負と言ってよい。3人いたら成り立たない。にらめっこで問答するうちに、問う者はハダカにされている。素肌が見えるし、体重も分かってしまう。なにもかも丸見えになる。しかも真剣に問う者ほど、丸見えになっていることに気付かない。優れた占者が言い当てることができるのは、この腕力、人間力ゆえであって、超能力など関係ないのだ、と最近になって気付いた。
マメと雑穀を売る店でマメを買った。小鳥用のヒマワリの種なども売っている店。近くにウナギの寝床がある。この道路と平行する道をつなぐ横筋の細道のことで、入り口は雑貨屋、なかはラーメン屋、飲み屋、古着屋、佃煮屋、惣菜屋、八百屋、魚屋、豆腐屋もある。魚屋は真っ赤に染めたタラコ、タコを並べている。昭和の味がしそうだ。インドの雑貨小物を売る店、骸骨なんかがついているブレスなどを並べる店もある。昼飯屋もあるが、こうした食べさせる店は、せいぜいがスツール3つ程度のカウンターの店。シモキタの昔と似ている。見慣れない店があった。垂れ布の隙間から、小机を挟んで向き合う女性ふたりがみえた。こちらを向いているのが占い師で、背が見えるのが客らしい。10分千円と看板が立てかけてあった。スパゲティを茹でる時間が、私の場合12分だから、ゆであがる前に終わりだ。私は貧乏性だから、時間が気になって上の空になりそう。町の占いでは学割が効く店は知っているけれど、これは初めてだった。
別建ての話に逸れて恐縮ですが、占い師と客の関係は興味深い。客が問う。それに答える占い師。インタビューも同じ事だけれど、一見、答える側が内蔵する、所有する、我が身の一部を取りだして、相手に渡す形である。私が思うに、それは表面上のことであり、問う者のほうが自身をさらけ出してしまうものなのだ。これは一対一の真剣勝負と言ってよい。3人いたら成り立たない。にらめっこで問答するうちに、問う者はハダカにされている。素肌が見えるし、体重も分かってしまう。なにもかも丸見えになる。しかも真剣に問う者ほど、丸見えになっていることに気付かない。優れた占者が言い当てることができるのは、この腕力、人間力ゆえであって、超能力など関係ないのだ、と最近になって気付いた。
笑いの種類
27-02-15 11:49 更新
創作でもっとも高度の能力を必要とするのが、受け手に笑いをもたらすことである。怒りや悲しみを伝えるほうが容易いというと語弊があるが、一直線に万人の胸に飛びこんでゆく。しかし笑いは一筋縄ではいかない。笑い転げる人がいる反面、くそ面白くもねえ、とそっぽを向く者もでる。笑いを作る芸術家を、私は花祭りのひな壇の最上段に飾りたい。笑いを醸し出せる俳優はすてきだ。そういう意味で選ぶと、男雛はフランスのルイ・ジューべ。女雛はアメリカのマリリン・モンロー。いまどきルイ・ジューべを知る人は少ないだろう。お二人とも故人であるが、芸術は永遠です。
と、これは枕で、今日話したいことは、笑いについての大発見についてです。『社会脳からみた認知症』というタイトルの伊古田俊夫先生の著作のなかに、笑いの分析を見つけました。この本は、あらためて読書評で紹介しますが、私の書架にある何冊もの笑い分析本とはまったく異質で、しかも納得の神髄があります。
認知症になると笑わなくなるということから、笑いを追っている。人が笑うためにはユーモアを理解することが必要で、落語を聞いて笑うのもおかしさが分かるから。一方、ユーモアに関係ない笑い、それは自虐的な笑い、作り笑いなどで、この笑いは、脳の中の別の部分、運動野(随意運動中枢がある)を使っているというのです。ユーモアを理解して笑うほうは、前頭葉など別の2カ所を作動させていて、運動野ではないから、自然とこみ上げてくる笑いだといいます。笑いは不眠症がなおるし、免疫力も強くなり、疼痛の緩和にも役立つのだと、書いてありました。
洋の東西を問わず、笑いの分析者は数多く、しかしそのすべてが文人によるものでした。脳の世紀と呼ばれる今世紀に入り、ますます進む脳内探検は、笑いの分野へも踏み込んできたのだという感慨を持ちました。
それで思い出しました、度重なる失意の入院生活の折々に、私が心血を注いでいたことは、回診の医者たち、巡回の看護師たち、掃除の係など、ベッドサイドに現れる人たちを短い一言で笑わせることでした。瞬間芸。よくまあ、これほど苦々しい顔になれるもんだ、とこっちも口がへの字になりそうな大先生が、片頬でかすかに漏らしてしまう笑みに、その日が猛烈嬉しくなってしまう。友人の夫が外科の勤務医で、陽気な患者は傷の治りが早い、と言っていたそうですから、陽気がどうであれ、また雪が降るにしても、良質な自然に湧く笑いとともに生活したいものです。
と、これは枕で、今日話したいことは、笑いについての大発見についてです。『社会脳からみた認知症』というタイトルの伊古田俊夫先生の著作のなかに、笑いの分析を見つけました。この本は、あらためて読書評で紹介しますが、私の書架にある何冊もの笑い分析本とはまったく異質で、しかも納得の神髄があります。
認知症になると笑わなくなるということから、笑いを追っている。人が笑うためにはユーモアを理解することが必要で、落語を聞いて笑うのもおかしさが分かるから。一方、ユーモアに関係ない笑い、それは自虐的な笑い、作り笑いなどで、この笑いは、脳の中の別の部分、運動野(随意運動中枢がある)を使っているというのです。ユーモアを理解して笑うほうは、前頭葉など別の2カ所を作動させていて、運動野ではないから、自然とこみ上げてくる笑いだといいます。笑いは不眠症がなおるし、免疫力も強くなり、疼痛の緩和にも役立つのだと、書いてありました。
洋の東西を問わず、笑いの分析者は数多く、しかしそのすべてが文人によるものでした。脳の世紀と呼ばれる今世紀に入り、ますます進む脳内探検は、笑いの分野へも踏み込んできたのだという感慨を持ちました。
それで思い出しました、度重なる失意の入院生活の折々に、私が心血を注いでいたことは、回診の医者たち、巡回の看護師たち、掃除の係など、ベッドサイドに現れる人たちを短い一言で笑わせることでした。瞬間芸。よくまあ、これほど苦々しい顔になれるもんだ、とこっちも口がへの字になりそうな大先生が、片頬でかすかに漏らしてしまう笑みに、その日が猛烈嬉しくなってしまう。友人の夫が外科の勤務医で、陽気な患者は傷の治りが早い、と言っていたそうですから、陽気がどうであれ、また雪が降るにしても、良質な自然に湧く笑いとともに生活したいものです。
禁じられた遊び
10-11-14 21:46 更新
いまごろ、半世紀以上前に作られた映画について、なんでかなと思うが書きたくなった。この映画は勿論モノクロ・スタンダードで87分という短い作品である。
パリ陥落。1940年。爆撃機が機銃掃射する、その機体にナチスのマークがハッキリと映る。当時の残虐な情景が、このワンシーンで定着する。一挙に両親と犬を失い、孤児となった5歳のポーレットが、死んだ犬を抱いてさまよううちに、農家の少年、ミシェルと出会う。やがて役人がやってきて施設に送られるまでのポーレットの、つかの間の日々が描かれる。それは、十字架を際限なく増やしてゆく、ポーレットにとっては遊びではない、まだはっきりと掴めてはいない「死」の確認だった。どうしても必要なことだったんだ、とルネ・クレマンは、たぶん思っていただろう。最初の幾つかのシーンと、ラストシーンのポーレットは、パリ育ちの5歳の女の子だ。いたいけな、可愛らしいブロンドの少女は、まるでドキュメントの実写かと感ずるほど自然で、涙が止まらない。
しかし、ミシェルと「ふたりの秘密のこと」をするときのポーレットは、見事に女である。そしてミシェルは恋する男である。少年も少女も、自覚はまったくない。しかし監督は男と女を描いている。女が欲しいものを、うっとりと見つめる、そのとき男は、万難を排して女の望みを叶えようとするのだ。女の欲しがる物は、次第に大きな、難しい物になってゆくが、男は、我が身を忘れて突き進む。さすがのフランス映画である。単純な作品ではない。
最近になって観ている人の中には「火垂るの墓」のフランス版だ、と見る向きもあるが、そうではない。
パリ陥落。1940年。爆撃機が機銃掃射する、その機体にナチスのマークがハッキリと映る。当時の残虐な情景が、このワンシーンで定着する。一挙に両親と犬を失い、孤児となった5歳のポーレットが、死んだ犬を抱いてさまよううちに、農家の少年、ミシェルと出会う。やがて役人がやってきて施設に送られるまでのポーレットの、つかの間の日々が描かれる。それは、十字架を際限なく増やしてゆく、ポーレットにとっては遊びではない、まだはっきりと掴めてはいない「死」の確認だった。どうしても必要なことだったんだ、とルネ・クレマンは、たぶん思っていただろう。最初の幾つかのシーンと、ラストシーンのポーレットは、パリ育ちの5歳の女の子だ。いたいけな、可愛らしいブロンドの少女は、まるでドキュメントの実写かと感ずるほど自然で、涙が止まらない。
しかし、ミシェルと「ふたりの秘密のこと」をするときのポーレットは、見事に女である。そしてミシェルは恋する男である。少年も少女も、自覚はまったくない。しかし監督は男と女を描いている。女が欲しいものを、うっとりと見つめる、そのとき男は、万難を排して女の望みを叶えようとするのだ。女の欲しがる物は、次第に大きな、難しい物になってゆくが、男は、我が身を忘れて突き進む。さすがのフランス映画である。単純な作品ではない。
最近になって観ている人の中には「火垂るの墓」のフランス版だ、と見る向きもあるが、そうではない。
台湾故宮博物館
09-11-14 10:46 更新
秋口に、上野の国立博物館へ、台湾故宮の文物を見に行った。会期終了直前に大慌てで駆けつけたのだ。話題の展示品は翡翠のハクサイである。翡翠の原石が持つ白と緑の濃淡をハクサイの葉に移して彫った名品。ところが目玉のハクサイは消えていて、かわりにハクサイを撮ったビデオがエンドレスで流れていた。人だかりがしていたが、わたしは特にハクサイ目当てでもなかったので、見ている人たちを眺めるのも一興だった。中国の人たちを多く見かけ、なかでも若者の姿が目についた。細部を指摘しながら話し合う姿が印象に残った。文物の物の中で目を見張ったのは刺繍だった。いったい針の太さはどんなものだろう、糸の細さに驚嘆した。絵画かと見まごうばかりの精密さとともに、その描写は単なるパターン化した刺繍ではなく奥深いものがある。唖然、呆然と見守った。
お目当てのものがない私は、思いがけず書の部屋で、ほとんどの時間を過ごして帰ってきた。解説がなければ読めない私である。この人を知っている、ということはほとんどない。たまに見つけるだけである。知らない人の文字をたんねんに見つめる。これは名品、と解説にある書を、すばらしいと感じることもない。そういうのは無理をしないことにしている。誰かがよい、と言ったら、誰かがよいと言った、と思うだけである。こうしたいい加減人間なのに、書を見て時間を忘れた。
紙に筆で縦書き。墨で書いている。人の手が書いている。毛筆には太さ、長さがあるから、大小さまざまだが、共通していることは、書き手の気持ち、心が筆を通して紙に置かれていることだ。よい風景を眺めて、よいなあ、と穏やかに書く。人に物事を依頼する。故人を偲ぶ。政治を云々する。さまざまな内容の文章が、ときにゆったりと穏やかに、あるいは涙にくれて書かれる。なかには、落ち着いて書きはじめたものの、途中から感情が激してきて、カッカとしながら彫りつけるように力を込めて書いた書もある。練りに練った詩文を、腕によりをかけて書く人もいる。
目の前に展示されているのは、ガラス越しの書だけれど、この人に会ってみたい、と慕わしく感じる書あり、あらぁ、ひねくれてる、意地が悪そうな人ね、と受け取る書もあった。海を隔てた大陸中国の地で、これほどの思いを溢れさせて暮らした文人たち。私はこのような人々と、書があるお陰で近々と会えた、と感じて感激した。
お目当てのものがない私は、思いがけず書の部屋で、ほとんどの時間を過ごして帰ってきた。解説がなければ読めない私である。この人を知っている、ということはほとんどない。たまに見つけるだけである。知らない人の文字をたんねんに見つめる。これは名品、と解説にある書を、すばらしいと感じることもない。そういうのは無理をしないことにしている。誰かがよい、と言ったら、誰かがよいと言った、と思うだけである。こうしたいい加減人間なのに、書を見て時間を忘れた。
紙に筆で縦書き。墨で書いている。人の手が書いている。毛筆には太さ、長さがあるから、大小さまざまだが、共通していることは、書き手の気持ち、心が筆を通して紙に置かれていることだ。よい風景を眺めて、よいなあ、と穏やかに書く。人に物事を依頼する。故人を偲ぶ。政治を云々する。さまざまな内容の文章が、ときにゆったりと穏やかに、あるいは涙にくれて書かれる。なかには、落ち着いて書きはじめたものの、途中から感情が激してきて、カッカとしながら彫りつけるように力を込めて書いた書もある。練りに練った詩文を、腕によりをかけて書く人もいる。
目の前に展示されているのは、ガラス越しの書だけれど、この人に会ってみたい、と慕わしく感じる書あり、あらぁ、ひねくれてる、意地が悪そうな人ね、と受け取る書もあった。海を隔てた大陸中国の地で、これほどの思いを溢れさせて暮らした文人たち。私はこのような人々と、書があるお陰で近々と会えた、と感じて感激した。
本のタイトル
04-11-14 10:29 更新
本には題名がある。これは中身の代表者の役目をしている。的確で簡潔。私はこれが好ましいし、望ましいと思っている。本の感想を書いてみて感じたのだけれど、中身とずれている、そぐわない題名がある。最近、といっても数年から十年以上にわたることだが、増えているように感じる。外国語の書物の翻訳本では、原書につけられた本来の題名から遠く離れたタイトルをつけていることも屡々見受ける。
もう一つの引っかかりは、副題をつける本が多く、これは増殖中、と言いたくなるほどの氾濫だ。内容との縁と所縁(ゆかり)はごくわずか、単に流行言葉である何文字かを正式題名として置き、副題として、だらだら、ぐだぐだ、中身を説明する。何やってんだ、と思う。出版社の販売戦略が根にあることは言うまでもないが、編集者と打ち合わせのときに著者が同意しているわけ? などと考えてしまう。ひどいものは、なんと表紙全体、ベタで内容を列記していた。これなら表紙を見ただけで開く手間が省けるというものだ。
他書のことを、あげつらう資格は私にはない。私自身も、これから出版する予定の小説本の題名に副題をつけることを、今から決めているのだから。「薬子 ー藤原種継の娘ー」という題名を考えている。薬子に藤原を被せたくない。しかし種継が手塩にかけた妖艶、有能、そしてファザコン娘なのだから、これ以外に私は置く言葉を思いつかない。それなら、この一行まとめて、一つの題名と言えるか。いや、題名は、あくまで「薬子」にしたい。題名はむずかしい。
もう一つの引っかかりは、副題をつける本が多く、これは増殖中、と言いたくなるほどの氾濫だ。内容との縁と所縁(ゆかり)はごくわずか、単に流行言葉である何文字かを正式題名として置き、副題として、だらだら、ぐだぐだ、中身を説明する。何やってんだ、と思う。出版社の販売戦略が根にあることは言うまでもないが、編集者と打ち合わせのときに著者が同意しているわけ? などと考えてしまう。ひどいものは、なんと表紙全体、ベタで内容を列記していた。これなら表紙を見ただけで開く手間が省けるというものだ。
他書のことを、あげつらう資格は私にはない。私自身も、これから出版する予定の小説本の題名に副題をつけることを、今から決めているのだから。「薬子 ー藤原種継の娘ー」という題名を考えている。薬子に藤原を被せたくない。しかし種継が手塩にかけた妖艶、有能、そしてファザコン娘なのだから、これ以外に私は置く言葉を思いつかない。それなら、この一行まとめて、一つの題名と言えるか。いや、題名は、あくまで「薬子」にしたい。題名はむずかしい。
図書館めぐり
03-11-14 15:51 更新
私が住む地域が二つの自治体の境界近くにあるために、両市の図書館を利用している。図書館で読書をして過ごすのではなく、リクエストした図書を受け取り、返本する利用法だ。持ち帰ると、まず表紙のクリーニングをする。読みはじめてからは、書き込みを見つけると消す。また破損箇所を見つけると、修理して返す。「ノド割れ」と言って、ページののり付け部分が剥がれている本は、繰り返し読まれてきた本に見かける破損で、私は、これを修理するのが、自慢みたいに聞こえたら、みっともないけれど、上手なのだ。のり付けして一晩、重石をする。翌日には、どこを修理したか、自分でも分からないくらいに、きれいになっている。図書館のカウンターに返すときは、知らん顔をしている。一度だけ、伝えたことがあった。それは他館から運んできてもらった本で、しかも開架棚ではなく、書庫に収納されていた本だった、図書館員にそっと伝えた、「この本、絶版です。古書市場に1冊、出てますけど1万8千円です。大事にお願い……」。これが普通なのか、私が利用する図書館の特徴なのか、頷いてくれたけれど、顔も上げなかった。私は歩数計のカウントを楽しみに歩きながら独り言をいう、「いいさ、いいんだよ」すると本の声が聞こえた、「まああぁぁ! 久しぶりに書庫から出して貰ったなぁ!」
紀行について
30-10-14 19:33 更新
吉川弘文館が発行している「本郷」11月・114号に芭蕉の「奥の細道」についての小文が載っている。これは、「人をあるく」シリーズ『松尾芭蕉と奥の細道』の著者、佐藤勝明氏が書いたものだ。「本郷」では、著者が自著にちなんだ話題のエッセイを書くことが多く、これが実に興味深い。佐藤氏は芭蕉が旅した奥の細道を何回も、微に入り細を穿つように辿りなぞり、考察していられる。バッタのように飛び飛びにほっつき歩き、抜けたところは抜かしたままの私とは雲泥の差である。それはともかく、芭蕉という人を、まだ、今ひとつ掴んでいないのだけれども、つまり正面から挨拶をする芭蕉さまの顔はわかるが、後ろ姿が、まだ見えていない、といったところだろうか。「奥の細道」は、一筋縄ではいかない、仕掛け、企みのある作品だと感じている。多くの芭蕉ファンがなぞり歩き、ここで詠んだのだ、と感じ入る。そういう楽しみをふんだんに提供している木立の陰に、深い闇をさりげなく置いている。
佐藤勝明氏が、このように書いていられる。「”細道”には文芸的な創作の部分が多く、芭蕉自身の旅を材料にはしていても、それとは別の物語的な作品になっていると見て間違いない」そうだろう、芭蕉は、そういうことをしているのだ。西行を愛し、「源氏物語」に一目置いていた芭蕉翁。いま書こうとしているカリブの紀行が念頭にある。
佐藤勝明氏が、このように書いていられる。「”細道”には文芸的な創作の部分が多く、芭蕉自身の旅を材料にはしていても、それとは別の物語的な作品になっていると見て間違いない」そうだろう、芭蕉は、そういうことをしているのだ。西行を愛し、「源氏物語」に一目置いていた芭蕉翁。いま書こうとしているカリブの紀行が念頭にある。
同じ道なのに
22-10-14 13:36 更新
先月の「道の不思議」の謎を解こうとして、ふたたび歩いた。この道は猛スピードで抜けて行く車が多い、いわゆる抜け道であって、実は私も抜け道として利用していたのだ。もともとは、地元の人が歩くための道だし、畑も作れない斜面を曲がりくねり、上下しながら隣の村落へ通じる、そういう農道を舗装したものだ。私は、車を運転している気持ちになって歩いてみた。運転しているつもりの私は、道路の曲がり具合、登りか下りか、そして角々に立つミラーに注意を向ける。ミラーは大切だ、これがないと対向車が見えないのだ。この道路には速度制限の標識や、道路標識などは一切ないから、問題はミラーだった。私はオレンジ色のポールについているミラーと並んで立ってみた。そこには新しい景色、はじめてみる風景が広がっていた。ススキ、ヤブカラシ、クズ、エノコログサの斜面の下に屋根が見えた。一般の家ではなさそう、お寺らしい。行ってみようかな。どこから降りるのかしら。何本もあるミラーごとに、私は新しい風景に出会った。対向車を知らせる役目のミラーは、こんな風景を映していたのだった。車に乗せて貰っているときは、ゆとりをもって眺められるが、運転しているときは、脇見は禁物、必要なところを見定めながら走る。ミラーに車影があるか、ないか。それだけを確認していたから、ミラーの立つ場所に限って、周囲の景色を見ていなかったのだ。
年を取って丸くなる
18-06-14 00:13 更新
あの人も、すっかり丸くなったねえ、と噂しあったことはないだろうか。あるいは、いやもう、年でしてね、丸くなりましたよ、などと自嘲気味に言ったりとか。ときどき丸くなる、と言うことについて考える。丸める、という言い方があって、頭を丸めたといえば、坊主になったのだ。数字を丸める、といえば端数を0,0,0として切り捨ててしまう。丸めるのは、団子だけではない。人も丸くなるのだろうか、ということだ。私は、ならないのではないかと思い始めている。気短で、すぐに腹を立てる。こうと思ったら、とことん通す。気が強い、突っかかる。こんな性分が、大福みたいになるか。
地元の図書館で、こんなことがあった。山口県の方が、山口の民話を書いた。その本を文房 夢類が出版したとき、この図書館へ寄贈しようとした。図書館員に、その旨を伝えたところ、遠くの県の民話は要りません、それに図書が溢れている、と断られた。この図書館はボランティアを受け入れず、地元の書店員が書店名を名札につけて働いている。なぜ、そのようなことをするのかは知らない。私は、書店員を避けて図書館員を選んで話したのだ。そうですか、と私は引き下がった。著者に言うと、遠くのものこそ読んで貰いたいのに、と怒った。同感、その通りなのだ。別の日に、別の図書館員に、このことを伝えた。すると、彼は「そんなことを言いましたか」と苦笑したが、それきりだった。なにもしようとはしなかった。
この図書館は、私が発行している「夢類」を地域の資料として受け入れ、開架に並べている。この数年間、なぜか開架に並べてくれないので、訊ねたが返事がない。数回にわたり訊ねたあと、私は中央図書館へメールを出した。翌日、電話があり、なんで直接、地元のウチに言ってくれないのか、中央なんかに言いつけてくれなくてもいいのに、と不満を露わにした。その後、数年間の「夢類」誌が見当たらないので、再度欲しいと言われた。そうですか、と私は、最新号までを渡したが、すでに絶版になってしまった号もあり、揃わなかった。見当たらないのではない、捨てたのだろうと私は諸々の現象から推測している。腹を立てることに躊躇しない私である。それが「そうですか」と引き下がったのだ。私は、丸くなったのだろうか?
ウニのようにトゲトゲだったのが、すべすべ大福になった、のかもしれない。そうかもしれませんが、中身は同じなのだった。人間、丸くなんかなれるもんじゃない。私は図書館関係の話題が出るたびに話し、書いてしまう。止めない。この「壷猫」は次号の「夢類」に載せるから、増殖を続ける。丸くなるのではない、沈潜するのだ。たちが悪い。
地元の図書館で、こんなことがあった。山口県の方が、山口の民話を書いた。その本を文房 夢類が出版したとき、この図書館へ寄贈しようとした。図書館員に、その旨を伝えたところ、遠くの県の民話は要りません、それに図書が溢れている、と断られた。この図書館はボランティアを受け入れず、地元の書店員が書店名を名札につけて働いている。なぜ、そのようなことをするのかは知らない。私は、書店員を避けて図書館員を選んで話したのだ。そうですか、と私は引き下がった。著者に言うと、遠くのものこそ読んで貰いたいのに、と怒った。同感、その通りなのだ。別の日に、別の図書館員に、このことを伝えた。すると、彼は「そんなことを言いましたか」と苦笑したが、それきりだった。なにもしようとはしなかった。
この図書館は、私が発行している「夢類」を地域の資料として受け入れ、開架に並べている。この数年間、なぜか開架に並べてくれないので、訊ねたが返事がない。数回にわたり訊ねたあと、私は中央図書館へメールを出した。翌日、電話があり、なんで直接、地元のウチに言ってくれないのか、中央なんかに言いつけてくれなくてもいいのに、と不満を露わにした。その後、数年間の「夢類」誌が見当たらないので、再度欲しいと言われた。そうですか、と私は、最新号までを渡したが、すでに絶版になってしまった号もあり、揃わなかった。見当たらないのではない、捨てたのだろうと私は諸々の現象から推測している。腹を立てることに躊躇しない私である。それが「そうですか」と引き下がったのだ。私は、丸くなったのだろうか?
ウニのようにトゲトゲだったのが、すべすべ大福になった、のかもしれない。そうかもしれませんが、中身は同じなのだった。人間、丸くなんかなれるもんじゃない。私は図書館関係の話題が出るたびに話し、書いてしまう。止めない。この「壷猫」は次号の「夢類」に載せるから、増殖を続ける。丸くなるのではない、沈潜するのだ。たちが悪い。
白内障手術後の影響
16-05-14 21:52 更新
私が白内障になったのは40代だった。医者はストレスが原因で、元には戻らない、点眼薬を処方するが効果は期待できないと言った。出会う人の顔が見えなくなり、視力はコンマ1を切った。日光は視界を白転させた。不思議なことに風呂場の湯気の中では見えるのだった。手術をしたが、高度な技術の手術であるにもかかわらず負担は少なかった。眼帯を取ったとき、まず目に入ったのは若い女性、看護師さんだった。輝く笑顔でかがみ込んで笑っていた。あ、ほくろが。と私は言った、看護師さんの頬のほくろが見えたのだ。皆さん、そうおっしゃいます、と言って看護師さんは笑った。相手の目玉も見えなかったのが、小さなほくろが見えた。そのとき教えてもらったことを、私は繰り返し思い出す。
生まれたばかりの赤ちゃんの水晶体は透明で、澄んだ水のようなものだそうだ。年を経るにつれて濁りが生じる。中年になると薄茶色になるという。赤ちゃんの目に映る世界と、大人が見る世界は違うんです。そういう説明だった。私の見る世界は、手術後透明になった。一点の曇りもない世界を目にすることが出来るようになった。濁った液体によって閉ざされていた視力は、眼内レンズの力もあり、左右とも1,2に回復した。病院を出て帰る途中、植え込みの木を見つめた。これが葉の色。初めて見る鮮やかな緑だった。赤ちゃんの目と同じ、透明な目で見ている、そう感じた。手術後10年あまり経ったいま、視力は維持されて、なんら問題なく過ごしている。私は感謝とともに、この曇りのない目に心をこめて、あらゆるものを見よう、人間を見よう、社会を見ようと思う。
生まれたばかりの赤ちゃんの水晶体は透明で、澄んだ水のようなものだそうだ。年を経るにつれて濁りが生じる。中年になると薄茶色になるという。赤ちゃんの目に映る世界と、大人が見る世界は違うんです。そういう説明だった。私の見る世界は、手術後透明になった。一点の曇りもない世界を目にすることが出来るようになった。濁った液体によって閉ざされていた視力は、眼内レンズの力もあり、左右とも1,2に回復した。病院を出て帰る途中、植え込みの木を見つめた。これが葉の色。初めて見る鮮やかな緑だった。赤ちゃんの目と同じ、透明な目で見ている、そう感じた。手術後10年あまり経ったいま、視力は維持されて、なんら問題なく過ごしている。私は感謝とともに、この曇りのない目に心をこめて、あらゆるものを見よう、人間を見よう、社会を見ようと思う。
土と地
09-05-14 22:22 更新
最近の建築をみていると、土台を作り、家の枠が出来上がると、その中を全部コンクリートで固めてしまう。これは、床を張ったあと、湿気が上がってこないので、非常に快適な住空間が約束される。また、家まわりも、昔は犬走りと呼んでいた軒下部分を同様にコンクリにしてしまう。大邸宅はいざ知らず、都会の宅地は狭いので、庭の部分はあってなきがごとしである。車1台分を確保できたら上々。また、一昔前の、余裕のある宅地に住む人は高齢であるから、草むしりの負担、はびこった庭木の手入れなどの負担に耐えられず、コンクリートにしてしまう場合も見かけるようになった。
こうなると、戸建てであっても、マンションと変わりのない住空間で、つまり土がないのだ。こうして、私が住む地域からも、春にのそのそと歩むガマガエルは消えて、もちろん蛇はいないし、毛虫も見かけなくなった。逆に、プランターは人気で、玄関まわりは色とりどりの花で溢れ、わずかの庭にはハナミズキの花が咲く。前に、大工さんから聞いたことだが、家ってものは、ある程度水気がないと立ってらんないもんなんだ、砂地じゃだめなんだ、ということを覚えている。土と地はちがう。プランターには土があるが、地ではない。地下に水の流れる、生きている地と親密に付き合うことは、生き物のすることで、とても自然なんだと思う。私は草むしりの負担を軽くするために砂利を使っているが、コンクリートで固めることはしない。砂利は大雨を受け入れてくれるし、余分に乾燥させないでくれる。地と付き合おう、地の声を聞こう。
こうなると、戸建てであっても、マンションと変わりのない住空間で、つまり土がないのだ。こうして、私が住む地域からも、春にのそのそと歩むガマガエルは消えて、もちろん蛇はいないし、毛虫も見かけなくなった。逆に、プランターは人気で、玄関まわりは色とりどりの花で溢れ、わずかの庭にはハナミズキの花が咲く。前に、大工さんから聞いたことだが、家ってものは、ある程度水気がないと立ってらんないもんなんだ、砂地じゃだめなんだ、ということを覚えている。土と地はちがう。プランターには土があるが、地ではない。地下に水の流れる、生きている地と親密に付き合うことは、生き物のすることで、とても自然なんだと思う。私は草むしりの負担を軽くするために砂利を使っているが、コンクリートで固めることはしない。砂利は大雨を受け入れてくれるし、余分に乾燥させないでくれる。地と付き合おう、地の声を聞こう。
東京とは
29-01-14 22:58 更新
東京とは何者か。山中湖を背にしていま、私は東京の中心地へレンズを向けている。おりしも都知事選の最中で、今夕は手元に選挙公報を広げている。16人の候補者が、それぞれの主張を書いている。16人全員が生き生きと興味深い自説を披露し、東京を良くしようとしている。そのうちの2人が東京オリンピック返上、中止を主張していた。オリンピック反対は、私だけかと思っていたが、細川さんも決定以前は反対だったのだ。決まったから、それなら東北と東京でやろうじゃないか、と言っている。原発反対を主張する人は、輸出禁止を含めて7人。原発問題に触れていない人が5人。異色の候補者として、例の発明家と並び、革命家という職業の人がいる。費用もかかり力も要る立候補をする人たちは、今の時点で尊敬してやまない。
選挙を眺めながら感じていることは、東京とは、場所的に東京地域があるが、それが東京のすべて、ではないということだ。地方にいて東京を眺めている人、東京について発言する人、東京と往復している人なども又、確かな東京人なのだ。日本の各地から東京を指さし、考えを述べる人たちも又、たしかな東京人だと私は思う。
選挙を眺めながら感じていることは、東京とは、場所的に東京地域があるが、それが東京のすべて、ではないということだ。地方にいて東京を眺めている人、東京について発言する人、東京と往復している人なども又、確かな東京人なのだ。日本の各地から東京を指さし、考えを述べる人たちも又、たしかな東京人だと私は思う。
新しい車の夢
20-01-14 21:30 更新
私は歩いているときに頭が活発に働く。だれでも同じかもしれない。知っているのはベートーベンで、彼は散歩が大好きだったという話だ。彼の散歩は、ちょっと独特であり、森の中をとんでもない早さでめったやたらと歩き回るのだそうだ、それも単独散歩らしい。これは散歩とは言えない姿に見えるが、これをすると曲想が湧くのだという。ベートーベン氏が頭にあるものだから、私も歩こうとする。しかし、しみったれた性分であるから、駅前に用足しに行くなどタダでは歩こうとしない。
歩きながら浮かんだのは、新しい車の白昼夢。私だけが持っている特別の車。燃料は核融合を使う。信じられない話だが、ITER(国際核融合実験施設)が無害のエネルギー源開発に成功したことを掴んだので、遠隔透視を使って入手したのだ。燃料源は海水である。トイレ、キッチン、ベッドなど生活空間があり十人程度は乗れるので怖がらないという約束が出来る人に限り乗せてあげる。自動操縦可能。激突しても、ボールのように弾み、傷つかない装置がついている。外気は遮断して良質の空気を生産循環している。いいなあ。
特徴は重力コントロール装置をつけていることで、これを作動させると駐車場の心配から解放されるのだ。つまり、空中に浮かべておく。乗りたいときはリモコンで誘導して地上に降ろす。実は、車で走れるが、本質は航空機である。水中、地上、空中、宇宙を自在に移動できるヴィークル。いいなあ。私は駅前をめざして気持ちよく歩き続ける。
私は、この車で自由自在に走り回り飛び回る。ステルスなんか真っ青になるハイレベルの忍者車で、レーダーなんて気にならぬ。どこを飛んでいても、空飛ぶ円盤に間違えられるようなヘマはしない。レーダーに映らないのだから、目視した航空機だけが大慌てをする程度だ。いままでは国内にくすぶっていたが、我が新車では地球一周なんて朝飯前なのだ。私はこみいった操作が嫌いなので、操縦は単純、おおむね音声操作。おまけに各国の言語を自動翻訳して送受信するから、交信は楽々。付け加えると、あんがいアウトロー的なので、出入国などは忍者モードで自由自在無断通過。
どこへ行こうかな。マッキンレーのてっぺんがいいな。マチュピチュというのをテレビで見た。あそこへ行ってみよう。アマゾンに行かなくては。忙しいなあ。日本海溝へもぐってこなくては。とりあえず地球面をくまなく回ることだ。国際宇宙ステーション訪問は、そのあとでよかろう。宇宙飛行士たちは船内を浮遊しているが、あんな子供だましは遊びだけにして、重力コントロール装置を起動させれば地上と同様の暮らしができるのだ。火星にも行きたいが、なにしろ年が年なので、あ、駅に着きました。
歩きながら浮かんだのは、新しい車の白昼夢。私だけが持っている特別の車。燃料は核融合を使う。信じられない話だが、ITER(国際核融合実験施設)が無害のエネルギー源開発に成功したことを掴んだので、遠隔透視を使って入手したのだ。燃料源は海水である。トイレ、キッチン、ベッドなど生活空間があり十人程度は乗れるので怖がらないという約束が出来る人に限り乗せてあげる。自動操縦可能。激突しても、ボールのように弾み、傷つかない装置がついている。外気は遮断して良質の空気を生産循環している。いいなあ。
特徴は重力コントロール装置をつけていることで、これを作動させると駐車場の心配から解放されるのだ。つまり、空中に浮かべておく。乗りたいときはリモコンで誘導して地上に降ろす。実は、車で走れるが、本質は航空機である。水中、地上、空中、宇宙を自在に移動できるヴィークル。いいなあ。私は駅前をめざして気持ちよく歩き続ける。
私は、この車で自由自在に走り回り飛び回る。ステルスなんか真っ青になるハイレベルの忍者車で、レーダーなんて気にならぬ。どこを飛んでいても、空飛ぶ円盤に間違えられるようなヘマはしない。レーダーに映らないのだから、目視した航空機だけが大慌てをする程度だ。いままでは国内にくすぶっていたが、我が新車では地球一周なんて朝飯前なのだ。私はこみいった操作が嫌いなので、操縦は単純、おおむね音声操作。おまけに各国の言語を自動翻訳して送受信するから、交信は楽々。付け加えると、あんがいアウトロー的なので、出入国などは忍者モードで自由自在無断通過。
どこへ行こうかな。マッキンレーのてっぺんがいいな。マチュピチュというのをテレビで見た。あそこへ行ってみよう。アマゾンに行かなくては。忙しいなあ。日本海溝へもぐってこなくては。とりあえず地球面をくまなく回ることだ。国際宇宙ステーション訪問は、そのあとでよかろう。宇宙飛行士たちは船内を浮遊しているが、あんな子供だましは遊びだけにして、重力コントロール装置を起動させれば地上と同様の暮らしができるのだ。火星にも行きたいが、なにしろ年が年なので、あ、駅に着きました。
車の夢
20-01-14 11:22 更新
車を降りてから、私は車の夢を見るようになった。
いままでも、数知れず運転している夢を見てきたが、車を降りてから見る車の夢は、苦しい。苦悩に満ちている。うなされる。夢の光景は同じだ。いつものように独りで自分の車を走らせている。私は道の行く手を見ている。前に来たことがある道だ。あれ? 今日は工事中らしい。通れない。
別の夜には、この道が一歩通行に変わっている。巨大トラックが道をふさいでいて通れないこともある。とにかく、非常な現実味を帯びて、通れない状況が具体的に現れるのだ。
この道の先に帰るべき家がある。しかし行かれないという困惑は、夢の中では絶望的な苦悩となって迫る。
年が明けて、また車の夢を見た。年明けの夢では、運転はしていなかった。ディーラーにいる。真っ赤な車、美しくも鮮やかなイタリアンレッドの小さな車が目の前にあり、なんだぁ、と私は笑っている。営業の人の声も姿もない。丸っこい、小さな赤い車だけがある。よかったじゃない! これだったら大丈夫。これで車に乗れるわ。もう諦めたのよ、本気で。一度止めた決心したのを覆すのは気が引けるけど、これに決めます。夢の中で私は結構、細かい気持ちの変化を味わっている。喜びが胸一杯に満ちて、幸福感に包まれた。
醒めたときの、信じられない、夢だったとは、という落ち込みはすさまじかった。私はどれほど車に密着して生活してきたかを、改めて噛みしめた。
いままでも、数知れず運転している夢を見てきたが、車を降りてから見る車の夢は、苦しい。苦悩に満ちている。うなされる。夢の光景は同じだ。いつものように独りで自分の車を走らせている。私は道の行く手を見ている。前に来たことがある道だ。あれ? 今日は工事中らしい。通れない。
別の夜には、この道が一歩通行に変わっている。巨大トラックが道をふさいでいて通れないこともある。とにかく、非常な現実味を帯びて、通れない状況が具体的に現れるのだ。
この道の先に帰るべき家がある。しかし行かれないという困惑は、夢の中では絶望的な苦悩となって迫る。
年が明けて、また車の夢を見た。年明けの夢では、運転はしていなかった。ディーラーにいる。真っ赤な車、美しくも鮮やかなイタリアンレッドの小さな車が目の前にあり、なんだぁ、と私は笑っている。営業の人の声も姿もない。丸っこい、小さな赤い車だけがある。よかったじゃない! これだったら大丈夫。これで車に乗れるわ。もう諦めたのよ、本気で。一度止めた決心したのを覆すのは気が引けるけど、これに決めます。夢の中で私は結構、細かい気持ちの変化を味わっている。喜びが胸一杯に満ちて、幸福感に包まれた。
醒めたときの、信じられない、夢だったとは、という落ち込みはすさまじかった。私はどれほど車に密着して生活してきたかを、改めて噛みしめた。
天国
11-11-12 00:37 更新
天国という。キリスト教文化圏の人たちが天国というときは、キリスト教を基本土台として天国を認識しているから、まったく問題がない。彼らには、ほんとうに天国は存在する。天国と、煉獄と、地獄が存在する。しかし、家に仏壇や神棚のある日本の人たちが天国というとき、なにを思っているのだろう、と私は不思議なのだ。人が亡くなったときに、天国で云々、と追悼の言葉を言う。二言目には天国だ。仏壇、神棚から、どんな天国を連想しているのだろう? それともクリスマスやハロウィーンの感覚で、人が亡くなったときだけ、キリスト教風になっているのだろうか? まさか。それはないだろう。
私には、天国はない。「死」から見えるのは、冥府である。黄泉の国である。そして三途の川、賽の河原である。日本の神話に根ざした、幼いときからなじんでいる世界が、この冥府である。この世界はほとんどフィクションから遊離しているので、確かな姿をしている。
私には、天国はない。「死」から見えるのは、冥府である。黄泉の国である。そして三途の川、賽の河原である。日本の神話に根ざした、幼いときからなじんでいる世界が、この冥府である。この世界はほとんどフィクションから遊離しているので、確かな姿をしている。
社説とコラム
30-06-12 11:42 更新
新聞には社説とコラムがある。朝日新聞なら天声人語、読売新聞は編集手帳、よみうり寸評、毎日新聞は余録をはじめ、膨大な数のコラムを擁する。東京新聞は筆洗。日本経済新聞は春秋。ここに、社の見識と人で言えば人格が現れる。この中の王者が朝日新聞の天声人語で、朝日新聞は、自ら書いている、「大学入試問題に非常に多くつかわれる天声人語。読んだり書きうつしたりすることで、国語や小論文に必要な論理性を身につけることが出来ます」。
天下の朝日と言われてきた朝日新聞の天声人語は、お手本だった。が、だいぶ前からおかしくなっている。いま、これを手本としていたらどうなることか。いまごろ言うか、と笑う声が聞こえるが、表だって誰も言わないことである。
力を抜いてきているのなら話は簡単だが、そうではない。まじめに書いているのは分かるのだ、一般読者のみならず、社内でも当然読んでいるだろうに、この「おかしさ」に気づくことがない。ここでいう「おかしさ」とは、面白い、笑いたくなる面白さではない。冷蔵庫から、おかずのパックを出して、お勝手にいる誰かの鼻先に持って行って訊ねる、これ、おかしくない? そういうおかしさ、である。おかしいよ。捨てたら? うん。ダメだね。と続く会話。腐ったら、鯛でもダメなのだ。腐敗は、内部、深部から発生し、崩壊するしかない。
私の鼻がどうかしているのかしら? 捨てた方がいいよ、と感じているのだが。これは社会の問題としないで、文学のジャンルに入れよう。
ついでに言うと、読売新聞は、あのとおりだが、意見の方向はそれとして健康体だ。いま一番魅力的で、溌溂として勢いがあるのが東京新聞だ。
天下の朝日と言われてきた朝日新聞の天声人語は、お手本だった。が、だいぶ前からおかしくなっている。いま、これを手本としていたらどうなることか。いまごろ言うか、と笑う声が聞こえるが、表だって誰も言わないことである。
力を抜いてきているのなら話は簡単だが、そうではない。まじめに書いているのは分かるのだ、一般読者のみならず、社内でも当然読んでいるだろうに、この「おかしさ」に気づくことがない。ここでいう「おかしさ」とは、面白い、笑いたくなる面白さではない。冷蔵庫から、おかずのパックを出して、お勝手にいる誰かの鼻先に持って行って訊ねる、これ、おかしくない? そういうおかしさ、である。おかしいよ。捨てたら? うん。ダメだね。と続く会話。腐ったら、鯛でもダメなのだ。腐敗は、内部、深部から発生し、崩壊するしかない。
私の鼻がどうかしているのかしら? 捨てた方がいいよ、と感じているのだが。これは社会の問題としないで、文学のジャンルに入れよう。
ついでに言うと、読売新聞は、あのとおりだが、意見の方向はそれとして健康体だ。いま一番魅力的で、溌溂として勢いがあるのが東京新聞だ。
ドラマ
10-06-12 22:42 更新
演劇、映画、TVドラマ、どれもが魅力で、ドラマ一筋に情熱を燃やしてきた。これが憑きものが落ちたかのように熱が冷めてしまい、我ながらとまどっている。結局は「感情の転がし」ではないか。人間、感情の波乗りで人生を送るのはもったいない。大切な事柄を決めるときに、感情を入れてはダメだ、と私は日頃自戒しているが、ドラマは、どうでもいいようなことで大騒ぎをしてみせる。およそ1年近くテレビを見ないで過ごし、最近、数局が映るようにしてもらったので大喜びで見始めるが、どうしたことか、つまらなくなって切ってしまう。とくにドラマを見るのが苦痛になった。気合いを入れて制作された映画は、これはよい。とてもよい。しかし、量産されるTVドラマは役者もいい加減で、学芸会だ。表情も表面だけの作り物で見ていられない。しかも、朝っぱらから叫びたて、怒鳴るのには辟易する。
人って、家庭で大声で怒鳴ったり、叫びたてたりはしないものだと思いませんか。戦争映画で怒鳴るのは結構だけれど、ホームドラマでは、止めてくれ、と思う。静かに台詞を言う自信が、脚本家にも演出にも、役者にもないのだ。ここまで書いてきて、やはり良いドラマを書きたくなった。
人って、家庭で大声で怒鳴ったり、叫びたてたりはしないものだと思いませんか。戦争映画で怒鳴るのは結構だけれど、ホームドラマでは、止めてくれ、と思う。静かに台詞を言う自信が、脚本家にも演出にも、役者にもないのだ。ここまで書いてきて、やはり良いドラマを書きたくなった。
小説の内側
08-05-12 08:59 更新
小沢一郎という政治家が罪に問われて、長い年月のあいだ政治活動の自由を奪われ、いわば座敷牢に入れられていた。こんど無罪判決がおりたが、控訴期限が明日に迫っている。控訴されればこの先、ふたたび自由を奪われる。そして寿命は限られているのだ。私は、この事件を追ってきた。その道中に、村木厚子という官僚が逮捕される事件が起きた。これは周知の通り、偽の障害者団体証明書を発行し、不正に郵便料金を安く用いたという、虚偽有印公文書作成・同行使罪だった。この事件も、発生直後の混沌とした時期から無罪となった時点まで見つめてきた。そして3.11 をきっかけに私は福島県知事だった佐藤栄佐久の辞職と逮捕、有罪の経緯を読んだ。核問題では、かつてアルベルト・シュバイツアーが核反対の旗印を掲げたとき、これを潰そうとして、シュバイツアーの身辺を洗い、暴き、彼を貶めようと画策したということも知った。世界を見渡せば古今、恐怖政治が蔓延していたのであり、事実は抹殺され、正義はなかった。イタリアを旅して震え上がる思いを味わったものだ。
ありがたいことに現在は、映像によって大政治家たちの表情を、態度を、つぶさに見ることができる。我を忘れて立腹してしまったのか、激怒してみせているのか。本心は違うが、事情に縛られての発言であるか。彼らの表情と仕草は、小説書きにとって魅せられる宝である。また、若手の未熟さ、性根の据わらぬ脆弱な表情。
ミス・ユニバースは、ミス・ユニバースに選ばれてから美しくなると言う。昔、山野愛子さんという美容家から直接伺った話だ。変わるのよ、と山野さんは言った。人は座によって変わる、このことについても映像は雄弁だ。
こうした進行形の人々を私は、奈良平安の人物群に重ねてみる。もう、ドキドキしてしまう。
ありがたいことに現在は、映像によって大政治家たちの表情を、態度を、つぶさに見ることができる。我を忘れて立腹してしまったのか、激怒してみせているのか。本心は違うが、事情に縛られての発言であるか。彼らの表情と仕草は、小説書きにとって魅せられる宝である。また、若手の未熟さ、性根の据わらぬ脆弱な表情。
ミス・ユニバースは、ミス・ユニバースに選ばれてから美しくなると言う。昔、山野愛子さんという美容家から直接伺った話だ。変わるのよ、と山野さんは言った。人は座によって変わる、このことについても映像は雄弁だ。
こうした進行形の人々を私は、奈良平安の人物群に重ねてみる。もう、ドキドキしてしまう。
ゆさぶりをかける
27-11-11 22:50 更新
揺さぶりをかける、とは、人間同士の場合、何をするのだろうか。相手の肩をつかんで、ゆさぶる。これが原点かもしれないが、脅しをかけるとか、相手を動揺させることをいう。
私は、こうした行為をサルから受けたことがある。2度もある。はじめの時は、西丹沢の山の中、山奥ではなくて人家との境界に立つ送電線のための鉄塔付近で、数匹のサルの群を見つけたときだ。私は、サルだ、と言って近寄って行ったら、群は逃げ出した。が、なかのいちばん大きなサルだけは逃げなかった。群が無事に逃げたのを見送ると、この大サルは、鉄塔の周囲に張り巡らせた金網に四つ足でつかまり、思いっきり揺さぶったのだ。真っ赤な顔で私を見ながら、揺さぶっている。その様子は、どうだ、オレさまはこんなに力持ちなんだぞ、恐れ入ったか! と言っているように見えた。わかったわよ、と言って私は近寄るのを止めた。
2度目は越後湯沢の土樽だった。畑の向こうが山で、山と畑は、わずかなススキの原でつながっていた。この畑に十数匹のサルがでていた。子ザルも2、3いる。私は、ここにサルが出ることを知っていたので、車中から望遠カメラを構えていた。期待以上に大勢出てきたので、私は車を出て、もっと近くに寄ろうと移動し始めたら、すぐに察知した群は、素早い動きで吸い込まれるように山に入ってしまった。残念。もっと寄りたかったなあ。ところが、大ザルだけは逃げなかった。この大ザルもまた、家族全員が山に入ったのを見届けるやいなや、山裾の1本の木につかまり、思いっきり揺さぶり出したのだ。私を見ながら揺さぶっている。あはは、怖くないわよ。と私は笑い、なおも近寄って行ったら山の暗がりへ飛び込んでしまった。サル心にも、揺さぶったら人間が動揺して逃げ出すんじゃないかと思ったに違いない。
この秋のこと、自宅の駐車場の隅にクモが巣を作った。次第に大きくなったクモは、黒と黄のまだらのジョロウグモである。見事な巣を張り、その中心に足を広げて陣取っている。私は、このジョロウグモの胴体を突ついてみた。ビックリして巣の中心から、端の隠れ家へ逃げ出すだろう。隠れ家を突き止めてみたい、それだけの理由で突ついたのである。するとジョロウグモは、意外な事に一歩も退かず、いきなり巣を揺さぶり出したのだ。揺れる、揺れる。中心にいるジョロウグモも前後に激しく揺れている。揺さぶる様子は、どうだっ 驚いたか! 怖いだろう! オレ様は、こんなに力が強いんだぞ、と言っているように見えた。クモがゆさぶりをかけるなんて、まさかといぶかり、何度も試したが、真剣にやっているのだった。
こうなってみると、ヒトもサルもジョロウグモも似たり寄ったりという生き物に見えてくる。
私は、こうした行為をサルから受けたことがある。2度もある。はじめの時は、西丹沢の山の中、山奥ではなくて人家との境界に立つ送電線のための鉄塔付近で、数匹のサルの群を見つけたときだ。私は、サルだ、と言って近寄って行ったら、群は逃げ出した。が、なかのいちばん大きなサルだけは逃げなかった。群が無事に逃げたのを見送ると、この大サルは、鉄塔の周囲に張り巡らせた金網に四つ足でつかまり、思いっきり揺さぶったのだ。真っ赤な顔で私を見ながら、揺さぶっている。その様子は、どうだ、オレさまはこんなに力持ちなんだぞ、恐れ入ったか! と言っているように見えた。わかったわよ、と言って私は近寄るのを止めた。
2度目は越後湯沢の土樽だった。畑の向こうが山で、山と畑は、わずかなススキの原でつながっていた。この畑に十数匹のサルがでていた。子ザルも2、3いる。私は、ここにサルが出ることを知っていたので、車中から望遠カメラを構えていた。期待以上に大勢出てきたので、私は車を出て、もっと近くに寄ろうと移動し始めたら、すぐに察知した群は、素早い動きで吸い込まれるように山に入ってしまった。残念。もっと寄りたかったなあ。ところが、大ザルだけは逃げなかった。この大ザルもまた、家族全員が山に入ったのを見届けるやいなや、山裾の1本の木につかまり、思いっきり揺さぶり出したのだ。私を見ながら揺さぶっている。あはは、怖くないわよ。と私は笑い、なおも近寄って行ったら山の暗がりへ飛び込んでしまった。サル心にも、揺さぶったら人間が動揺して逃げ出すんじゃないかと思ったに違いない。
この秋のこと、自宅の駐車場の隅にクモが巣を作った。次第に大きくなったクモは、黒と黄のまだらのジョロウグモである。見事な巣を張り、その中心に足を広げて陣取っている。私は、このジョロウグモの胴体を突ついてみた。ビックリして巣の中心から、端の隠れ家へ逃げ出すだろう。隠れ家を突き止めてみたい、それだけの理由で突ついたのである。するとジョロウグモは、意外な事に一歩も退かず、いきなり巣を揺さぶり出したのだ。揺れる、揺れる。中心にいるジョロウグモも前後に激しく揺れている。揺さぶる様子は、どうだっ 驚いたか! 怖いだろう! オレ様は、こんなに力が強いんだぞ、と言っているように見えた。クモがゆさぶりをかけるなんて、まさかといぶかり、何度も試したが、真剣にやっているのだった。
こうなってみると、ヒトもサルもジョロウグモも似たり寄ったりという生き物に見えてくる。
ものさし鳥
20-10-11 09:09 更新
ものさし鳥という鳥がいる。3羽いる。スズメ、ハト、カラス。野鳥観察の本に出ていた。はじめて見かけたきれいな小鳥。名前を知りたいな。野鳥を観察する人たちは、実によく名前を知っている。双眼鏡を胸にさげてあるく野鳥博士に、なんて名前ですか? と訊ねると喜んで教えてくださる。そのときに、色、声とともに大事なのが大きさ。その鳥はスズメくらいの大きさでしたか、ハトと同じくらいでしたか、などと訊ねられる。声は聞かなかった、胸が白かったけど、あとはわからなかった、などとあやふやなものだが、この問いには、自信を持って答えられるのが普通の人たちである。ハトです! ここから丁寧な観察がスタートする。
ものさし鳥を知ってから、そういえば私も、自分用のものさし鳥を持って生きてきたわけだ、と思い至った。それはスズメやハトと同じくらいに、ありきたりのもの。たとえば「女」。だれかの価値観を知るときに、女というものさしを当ててみるとわかる部分がある。女のくせに、それでも女か、などと言われると、一発でその人の地金が見えてくる。女性でも、女のくせに、という人は結構いるものだ。この物差しを使って、世間の常識という鋳型のなかに安住している人種と、常識にとらわれない人種を識別してきた。世界中に、さまざまな物差しを持つ人たちがいる。ひそかに懐に忍ばせ、あるいは大きく振りかざして。
ものさし鳥を知ってから、そういえば私も、自分用のものさし鳥を持って生きてきたわけだ、と思い至った。それはスズメやハトと同じくらいに、ありきたりのもの。たとえば「女」。だれかの価値観を知るときに、女というものさしを当ててみるとわかる部分がある。女のくせに、それでも女か、などと言われると、一発でその人の地金が見えてくる。女性でも、女のくせに、という人は結構いるものだ。この物差しを使って、世間の常識という鋳型のなかに安住している人種と、常識にとらわれない人種を識別してきた。世界中に、さまざまな物差しを持つ人たちがいる。ひそかに懐に忍ばせ、あるいは大きく振りかざして。
方位磁石
18-10-11 21:17 更新
先頃買った方位磁石だが、私にとっては無用の装置が多すぎた。私は東西南北がわかればよかった。窓から外を眺める、南側とはわかるけど、すこし西に傾いていないかしら、そんな疑問がわいたときに窓辺に方位磁石を置いて針の揺れが止まるのを待つ。これで充分だ。買い替えたのは、針がつっかえて動かなくなったからだった。それが、新規購入の代物は、照準機のような仕掛けがついていて、実にものものしい。細い針金の線と円盤に穿たれた細い溝とを合わせて、はるか遠くの物体と合わせる。これは銃の照準と同じやりかた。太重斉に見せたら、これは登山用だ、と言って使い方を教えてくれた。目指す地点に合わせておき、山に登る。しかしブッシュあり谷あり川あり、常に目指す地点が見えているわけではない。このとき、見定めておいた方位が役立つというのである。納得はいったが、本格的な登山は夢のまた夢、ごつい磁石を机の上に置いて文鎮がわりにした。こうして眺めるうちに発見したことがある。
人生の大目的、とおおげさに構えるもよし、大災害復興を置いてもよいし、身近な人間関係のいざこざ解決を置いてみるのもよい。これに照準を当てる。目的地方位がこれで決まるのである。行く手を確認したあと、右に曲がり、左に折れて、と複雑な道を辿ろうが、目先のことで、ああ言った、こう言われた、とあろうが、目的の地点に向かうことだ。揺るぎはない。当たり前のことだけれど、大勢で取りかかっているような場合、目的が逸れて、途中の事柄が目的化してしまうこともある。見定めた目的の地を目指す。当たり前だけれど難しい。方位磁石はいま、文鎮となって本のページを押さえながら、人の生き方について語りかけてくれる。
人生の大目的、とおおげさに構えるもよし、大災害復興を置いてもよいし、身近な人間関係のいざこざ解決を置いてみるのもよい。これに照準を当てる。目的地方位がこれで決まるのである。行く手を確認したあと、右に曲がり、左に折れて、と複雑な道を辿ろうが、目先のことで、ああ言った、こう言われた、とあろうが、目的の地点に向かうことだ。揺るぎはない。当たり前のことだけれど、大勢で取りかかっているような場合、目的が逸れて、途中の事柄が目的化してしまうこともある。見定めた目的の地を目指す。当たり前だけれど難しい。方位磁石はいま、文鎮となって本のページを押さえながら、人の生き方について語りかけてくれる。
昼の脳 夜の脳
16-10-11 00:18 更新
ながいこと夢を見ていなかった。就寝時間が遅く、横になったとたんに意識がなくなるような眠り方をしてきた。遅く寝るのに朝が早い。4時には自然に目覚めてしまう。睡眠時間が極端に短くなっている。昼寝をする日もあるから睡眠不足を感じたことはない。これでよいと思って来たのだが、最近になって、たまたま11時くらいに寝る日が続いた。11時に寝たら早く目覚めるはずが、そうはならずに4時過ぎまで寝てしまった。
話はここからである。夢を見た。それも賑やかな多種多様な場面の夢満載、そして目覚めたときには夢を見たことは感じているが夢の中身は消えている。何日か繰り返して悟ったことは、やはり夢は見た方がよいのだなあ、ということだった。昼間の生活のなかの、事務的な事柄以外の部分が活発になる、と感じた。左右の脳がそれぞれに担当している役割があるように、昼の脳、夜の脳の担当分野があるらしいと感じた。昼と夜。光と影。
こういう、普通の人に無視されるような戯言を思いつくのが夢の力ではないかと私は、まじめに考えている。
話はここからである。夢を見た。それも賑やかな多種多様な場面の夢満載、そして目覚めたときには夢を見たことは感じているが夢の中身は消えている。何日か繰り返して悟ったことは、やはり夢は見た方がよいのだなあ、ということだった。昼間の生活のなかの、事務的な事柄以外の部分が活発になる、と感じた。左右の脳がそれぞれに担当している役割があるように、昼の脳、夜の脳の担当分野があるらしいと感じた。昼と夜。光と影。
こういう、普通の人に無視されるような戯言を思いつくのが夢の力ではないかと私は、まじめに考えている。
同じ空
03-10-11 23:01 更新
道に立って東を見る。日の出だ、紅色に染まっている。見上げると今日も快晴、秋の雲は高い。しかし、それは切り紙細工のように、ハサミで切り取ったような空と雲である。
切り口は、我が家の屋根であり、隣家の屋根屋根、縦横に張り巡らされている配電線の黒い筋、電波の柱であり............。
私は、頭の中で切り紙を消してみる。目の先の道路標識も、遥か遠くの建物も、水道タンクも、すべて消してしまおう。
まあああああ! なんと美しい。東京だって川崎だって、おなじなんだ、山中湖の鏡のような湖面に映る空と。金色に波打つ越後の稲田を覆う空と。
タクラマカン砂漠の空も、カンサスの空も、アリゾナの空も、東京の空とおなじはずだ。
切り口は、我が家の屋根であり、隣家の屋根屋根、縦横に張り巡らされている配電線の黒い筋、電波の柱であり............。
私は、頭の中で切り紙を消してみる。目の先の道路標識も、遥か遠くの建物も、水道タンクも、すべて消してしまおう。
まあああああ! なんと美しい。東京だって川崎だって、おなじなんだ、山中湖の鏡のような湖面に映る空と。金色に波打つ越後の稲田を覆う空と。
タクラマカン砂漠の空も、カンサスの空も、アリゾナの空も、東京の空とおなじはずだ。
女心
07-08-11 22:36 更新
福島原発.......福1と略称が生まれた、この大事故について、8月6日原爆の日には、とくに思いが押し寄せて、式典の実況とともに1時間を過ごした。これから先、ますます福1が出てくるに違いない、今回はそれは置いておいて、昔の思い出を記す気になった。昔の「思い出」「女心」とでたら、このあとに来るのは「恋」。そう思うでせう。残念でした。はずれ、です。
ライターとしてプロダクションで仕事をしていた時代のこと、プロデューサーに取材に行ってこいと言われた。場所は新宿歌舞伎町、時は深夜。TVドラマ作りとは畑違いの方面の小説書きの男性に白羽の矢を立てたが、即座に同行を断られた。もうひとり、似たような男性を誘ったが、はっきり逃げられてしまった。軟弱な者どもである。単独で出かけたが、もともと生まれた地域から近い繁華街という認識なので気楽である。たいていの場所は歩き回った路地である。が、いつ何が起きてもおかしくない緊迫した空気が漲る澱みが見え、猥雑であり、きわめて美しいシーンもあるのだった。そして地方から物珍しげに訪れた男たちにとっては、そのような色合いは片鱗も見えずただ、金を出せば楽しめる明るい入り口が無数に開いている世界である。見せてよ、と私は言った、キップ売りの男は答えた、止めてやってね。男になら見せるよ、でも女にって、辛いんだよね。これだけ言ってもらえば充分だった。私は反省し、学んだ。痛々しい女心に触れた。キップ売りの男の心も、優しかった。みんなが、すべてを承知していた。承知しながら、生きなければならないことも分かっていた。私の心が抱きしめる女心、そして深夜の歌舞伎町。
ライターとしてプロダクションで仕事をしていた時代のこと、プロデューサーに取材に行ってこいと言われた。場所は新宿歌舞伎町、時は深夜。TVドラマ作りとは畑違いの方面の小説書きの男性に白羽の矢を立てたが、即座に同行を断られた。もうひとり、似たような男性を誘ったが、はっきり逃げられてしまった。軟弱な者どもである。単独で出かけたが、もともと生まれた地域から近い繁華街という認識なので気楽である。たいていの場所は歩き回った路地である。が、いつ何が起きてもおかしくない緊迫した空気が漲る澱みが見え、猥雑であり、きわめて美しいシーンもあるのだった。そして地方から物珍しげに訪れた男たちにとっては、そのような色合いは片鱗も見えずただ、金を出せば楽しめる明るい入り口が無数に開いている世界である。見せてよ、と私は言った、キップ売りの男は答えた、止めてやってね。男になら見せるよ、でも女にって、辛いんだよね。これだけ言ってもらえば充分だった。私は反省し、学んだ。痛々しい女心に触れた。キップ売りの男の心も、優しかった。みんなが、すべてを承知していた。承知しながら、生きなければならないことも分かっていた。私の心が抱きしめる女心、そして深夜の歌舞伎町。