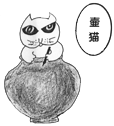November 2014
年末の選挙
27-11-14 10:21 更新 カテゴリ:主張・世相
国民が、一人一票の選挙権をつかって投票した総数の中で、現政権に投票した数よりも、野党に投票した数のほうが多いと聞いている。安倍政権が始まった瞬間から、不満である国民のほうが多かった。野党が結束して立ち向かえば、国民の総意が政権に反映される、と野党は主張している。その通りなのだが、今回は苦々しい気持ちで野党を見ている。いつもなら応援するのだが、今回は素直になれない。その理由は、野田佳彦前首相が、民主党内閣の時に、民主党支持の核心の部分を破棄して、まるで安倍さんが喋っているのではないか、と耳を疑うような転換をした故である。当時も、野田よ、だったら自民へ行け、という怒りの声があったのだ。あのとき民主党は、なぜ支持されたのだろう。主張する政策を支持したのだ。肝心の政策内容を変えるのであれば、そのときこそ総選挙をすべきではないか。夜陰、誰かにそそのかされて方針を転換か、とも罵倒された野田。こうした連中を含む民主党は、支持できない。自民も悪質だ。ウチワだ、ワインだ、ネギだ、など、どの議員もやっているようなことで2名を辞任に追い込んでおきながら、三権分立に抵触する行為を犯した片山さつきを沈黙の鍋底に隠した。それを知らないメディアではないはず。黙っているのは、荷担しているのだ。NHKはいつものとおり悪質だ。今回の選挙は、アベノミクスを評価しているか、どうかが問題です、と枕詞のように繰り返している。ここに有権者の目を引きつけようという魂胆が丸見えだ。問題は、腐敗しきっている安倍政権、野田のような変節漢を含む民主党、うじうじした小競り合いに明け暮れている他のみんな。いったい、この日本をどうすればいい? 選挙よりも、このことを国民が考えなければ始まらない。ひとりのこらず白票を入れたらいい。
禁じられた遊び
10-11-14 21:46 更新 カテゴリ:文学
いまごろ、半世紀以上前に作られた映画について、なんでかなと思うが書きたくなった。この映画は勿論モノクロ・スタンダードで87分という短い作品である。
パリ陥落。1940年。爆撃機が機銃掃射する、その機体にナチスのマークがハッキリと映る。当時の残虐な情景が、このワンシーンで定着する。一挙に両親と犬を失い、孤児となった5歳のポーレットが、死んだ犬を抱いてさまよううちに、農家の少年、ミシェルと出会う。やがて役人がやってきて施設に送られるまでのポーレットの、つかの間の日々が描かれる。それは、十字架を際限なく増やしてゆく、ポーレットにとっては遊びではない、まだはっきりと掴めてはいない「死」の確認だった。どうしても必要なことだったんだ、とルネ・クレマンは、たぶん思っていただろう。最初の幾つかのシーンと、ラストシーンのポーレットは、パリ育ちの5歳の女の子だ。いたいけな、可愛らしいブロンドの少女は、まるでドキュメントの実写かと感ずるほど自然で、涙が止まらない。
しかし、ミシェルと「ふたりの秘密のこと」をするときのポーレットは、見事に女である。そしてミシェルは恋する男である。少年も少女も、自覚はまったくない。しかし監督は男と女を描いている。女が欲しいものを、うっとりと見つめる、そのとき男は、万難を排して女の望みを叶えようとするのだ。女の欲しがる物は、次第に大きな、難しい物になってゆくが、男は、我が身を忘れて突き進む。さすがのフランス映画である。単純な作品ではない。
最近になって観ている人の中には「火垂るの墓」のフランス版だ、と見る向きもあるが、そうではない。
パリ陥落。1940年。爆撃機が機銃掃射する、その機体にナチスのマークがハッキリと映る。当時の残虐な情景が、このワンシーンで定着する。一挙に両親と犬を失い、孤児となった5歳のポーレットが、死んだ犬を抱いてさまよううちに、農家の少年、ミシェルと出会う。やがて役人がやってきて施設に送られるまでのポーレットの、つかの間の日々が描かれる。それは、十字架を際限なく増やしてゆく、ポーレットにとっては遊びではない、まだはっきりと掴めてはいない「死」の確認だった。どうしても必要なことだったんだ、とルネ・クレマンは、たぶん思っていただろう。最初の幾つかのシーンと、ラストシーンのポーレットは、パリ育ちの5歳の女の子だ。いたいけな、可愛らしいブロンドの少女は、まるでドキュメントの実写かと感ずるほど自然で、涙が止まらない。
しかし、ミシェルと「ふたりの秘密のこと」をするときのポーレットは、見事に女である。そしてミシェルは恋する男である。少年も少女も、自覚はまったくない。しかし監督は男と女を描いている。女が欲しいものを、うっとりと見つめる、そのとき男は、万難を排して女の望みを叶えようとするのだ。女の欲しがる物は、次第に大きな、難しい物になってゆくが、男は、我が身を忘れて突き進む。さすがのフランス映画である。単純な作品ではない。
最近になって観ている人の中には「火垂るの墓」のフランス版だ、と見る向きもあるが、そうではない。
台湾故宮博物館
09-11-14 10:46 更新 カテゴリ:文学
秋口に、上野の国立博物館へ、台湾故宮の文物を見に行った。会期終了直前に大慌てで駆けつけたのだ。話題の展示品は翡翠のハクサイである。翡翠の原石が持つ白と緑の濃淡をハクサイの葉に移して彫った名品。ところが目玉のハクサイは消えていて、かわりにハクサイを撮ったビデオがエンドレスで流れていた。人だかりがしていたが、わたしは特にハクサイ目当てでもなかったので、見ている人たちを眺めるのも一興だった。中国の人たちを多く見かけ、なかでも若者の姿が目についた。細部を指摘しながら話し合う姿が印象に残った。文物の物の中で目を見張ったのは刺繍だった。いったい針の太さはどんなものだろう、糸の細さに驚嘆した。絵画かと見まごうばかりの精密さとともに、その描写は単なるパターン化した刺繍ではなく奥深いものがある。唖然、呆然と見守った。
お目当てのものがない私は、思いがけず書の部屋で、ほとんどの時間を過ごして帰ってきた。解説がなければ読めない私である。この人を知っている、ということはほとんどない。たまに見つけるだけである。知らない人の文字をたんねんに見つめる。これは名品、と解説にある書を、すばらしいと感じることもない。そういうのは無理をしないことにしている。誰かがよい、と言ったら、誰かがよいと言った、と思うだけである。こうしたいい加減人間なのに、書を見て時間を忘れた。
紙に筆で縦書き。墨で書いている。人の手が書いている。毛筆には太さ、長さがあるから、大小さまざまだが、共通していることは、書き手の気持ち、心が筆を通して紙に置かれていることだ。よい風景を眺めて、よいなあ、と穏やかに書く。人に物事を依頼する。故人を偲ぶ。政治を云々する。さまざまな内容の文章が、ときにゆったりと穏やかに、あるいは涙にくれて書かれる。なかには、落ち着いて書きはじめたものの、途中から感情が激してきて、カッカとしながら彫りつけるように力を込めて書いた書もある。練りに練った詩文を、腕によりをかけて書く人もいる。
目の前に展示されているのは、ガラス越しの書だけれど、この人に会ってみたい、と慕わしく感じる書あり、あらぁ、ひねくれてる、意地が悪そうな人ね、と受け取る書もあった。海を隔てた大陸中国の地で、これほどの思いを溢れさせて暮らした文人たち。私はこのような人々と、書があるお陰で近々と会えた、と感じて感激した。
お目当てのものがない私は、思いがけず書の部屋で、ほとんどの時間を過ごして帰ってきた。解説がなければ読めない私である。この人を知っている、ということはほとんどない。たまに見つけるだけである。知らない人の文字をたんねんに見つめる。これは名品、と解説にある書を、すばらしいと感じることもない。そういうのは無理をしないことにしている。誰かがよい、と言ったら、誰かがよいと言った、と思うだけである。こうしたいい加減人間なのに、書を見て時間を忘れた。
紙に筆で縦書き。墨で書いている。人の手が書いている。毛筆には太さ、長さがあるから、大小さまざまだが、共通していることは、書き手の気持ち、心が筆を通して紙に置かれていることだ。よい風景を眺めて、よいなあ、と穏やかに書く。人に物事を依頼する。故人を偲ぶ。政治を云々する。さまざまな内容の文章が、ときにゆったりと穏やかに、あるいは涙にくれて書かれる。なかには、落ち着いて書きはじめたものの、途中から感情が激してきて、カッカとしながら彫りつけるように力を込めて書いた書もある。練りに練った詩文を、腕によりをかけて書く人もいる。
目の前に展示されているのは、ガラス越しの書だけれど、この人に会ってみたい、と慕わしく感じる書あり、あらぁ、ひねくれてる、意地が悪そうな人ね、と受け取る書もあった。海を隔てた大陸中国の地で、これほどの思いを溢れさせて暮らした文人たち。私はこのような人々と、書があるお陰で近々と会えた、と感じて感激した。
本のタイトル
04-11-14 10:29 更新 カテゴリ:文学
本には題名がある。これは中身の代表者の役目をしている。的確で簡潔。私はこれが好ましいし、望ましいと思っている。本の感想を書いてみて感じたのだけれど、中身とずれている、そぐわない題名がある。最近、といっても数年から十年以上にわたることだが、増えているように感じる。外国語の書物の翻訳本では、原書につけられた本来の題名から遠く離れたタイトルをつけていることも屡々見受ける。
もう一つの引っかかりは、副題をつける本が多く、これは増殖中、と言いたくなるほどの氾濫だ。内容との縁と所縁(ゆかり)はごくわずか、単に流行言葉である何文字かを正式題名として置き、副題として、だらだら、ぐだぐだ、中身を説明する。何やってんだ、と思う。出版社の販売戦略が根にあることは言うまでもないが、編集者と打ち合わせのときに著者が同意しているわけ? などと考えてしまう。ひどいものは、なんと表紙全体、ベタで内容を列記していた。これなら表紙を見ただけで開く手間が省けるというものだ。
他書のことを、あげつらう資格は私にはない。私自身も、これから出版する予定の小説本の題名に副題をつけることを、今から決めているのだから。「薬子 ー藤原種継の娘ー」という題名を考えている。薬子に藤原を被せたくない。しかし種継が手塩にかけた妖艶、有能、そしてファザコン娘なのだから、これ以外に私は置く言葉を思いつかない。それなら、この一行まとめて、一つの題名と言えるか。いや、題名は、あくまで「薬子」にしたい。題名はむずかしい。
もう一つの引っかかりは、副題をつける本が多く、これは増殖中、と言いたくなるほどの氾濫だ。内容との縁と所縁(ゆかり)はごくわずか、単に流行言葉である何文字かを正式題名として置き、副題として、だらだら、ぐだぐだ、中身を説明する。何やってんだ、と思う。出版社の販売戦略が根にあることは言うまでもないが、編集者と打ち合わせのときに著者が同意しているわけ? などと考えてしまう。ひどいものは、なんと表紙全体、ベタで内容を列記していた。これなら表紙を見ただけで開く手間が省けるというものだ。
他書のことを、あげつらう資格は私にはない。私自身も、これから出版する予定の小説本の題名に副題をつけることを、今から決めているのだから。「薬子 ー藤原種継の娘ー」という題名を考えている。薬子に藤原を被せたくない。しかし種継が手塩にかけた妖艶、有能、そしてファザコン娘なのだから、これ以外に私は置く言葉を思いつかない。それなら、この一行まとめて、一つの題名と言えるか。いや、題名は、あくまで「薬子」にしたい。題名はむずかしい。
図書館めぐり
03-11-14 15:51 更新 カテゴリ:文学
私が住む地域が二つの自治体の境界近くにあるために、両市の図書館を利用している。図書館で読書をして過ごすのではなく、リクエストした図書を受け取り、返本する利用法だ。持ち帰ると、まず表紙のクリーニングをする。読みはじめてからは、書き込みを見つけると消す。また破損箇所を見つけると、修理して返す。「ノド割れ」と言って、ページののり付け部分が剥がれている本は、繰り返し読まれてきた本に見かける破損で、私は、これを修理するのが、自慢みたいに聞こえたら、みっともないけれど、上手なのだ。のり付けして一晩、重石をする。翌日には、どこを修理したか、自分でも分からないくらいに、きれいになっている。図書館のカウンターに返すときは、知らん顔をしている。一度だけ、伝えたことがあった。それは他館から運んできてもらった本で、しかも開架棚ではなく、書庫に収納されていた本だった、図書館員にそっと伝えた、「この本、絶版です。古書市場に1冊、出てますけど1万8千円です。大事にお願い……」。これが普通なのか、私が利用する図書館の特徴なのか、頷いてくれたけれど、顔も上げなかった。私は歩数計のカウントを楽しみに歩きながら独り言をいう、「いいさ、いいんだよ」すると本の声が聞こえた、「まああぁぁ! 久しぶりに書庫から出して貰ったなぁ!」