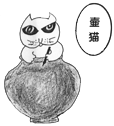旅の日常 日常の旅
07-06-18 09:00 更新 カテゴリ:主張
在るはず、と書架を彷徨うが見つからぬ。梅雨入りの翌朝に偶感として記す芭蕉の言葉。
芭蕉が許六との別れに臨み与えた言葉、と覚えているのだが。
「古人の跡をもとめず 古人の求たる所を もとめよ」
これは、もとは空海が言ったことという、有名な句である。
空海から発して芭蕉が許六に渡す、それを後世、胸にたたむ。
奥の細道をたどる旅、として芭蕉の名作『奥の細道』で芭蕉が実際に歩き辿った道筋をたどり歩く人々があとを絶たない。
たまたま、ここは最上川だなあと、川べりに佇み芭蕉の句、蕪村の句を思うことはあったが、道筋をなぞり歩くことを思いついたことはない。
梅雨どきである、庭石が濡れて潤いのある輝きを見せている朝。
紀行『笈の小文』を開きます。和歌山の紀三井寺のあたりで、旅の心を語っている、
「猶栖をさりて器物のねがひなし。空手なれば途中の愁もなし。寛歩駕にかへ、晩食肉よりも甘し。とまるべき道にかぎりなく、立べき朝に時なし。只一日のねがひ二つのみ。こよひ能宿からん、草鞋のわが足によろしきを求めんと計は、いさ丶かのおもひなり。時々気を転じ、日々に情をあらたむ。もしわずかに風雅ある人に出合たる、悦かぎりなし。日比は古めかしく、かたくななりと悪み捨たる程の人も、邊土の道づれにかたりあひ、はにふ・むぐらのうちにて見出したるなど、瓦石のうちに玉を拾ひ、泥中に金を得たる心地して、物にも書付、人にもかたらんとおもふぞ、又是旅のひとつなりかし」
生涯寓居の庇を借り、車を降りてのちは寛歩に頼り、とまるべき道にかぎりなく、立べき朝に時なし。これが今のありさま故、芭蕉の心が身に染み渡る。外目には一所に居着き暮らすかに映ろうとも心は片雲に漂う。旅の喜びの極めつけは、芭蕉さまが言われる通り、辺土のうちに語り合い、瓦石のうちに玉を拾う心地するところにあり、のちのち幾たびも思い出す宝である。
夢を、抱えている。頼る寛歩も不如意となるだろう、いつかの暁に、小さな葎姿の図書室を作り、誰となく入り来たり出でゆく道すがらの淀みのうたかたとすることだ、玉を得たる心地を味わう縁となるやも知れぬ。わが身は動けずとも、これも旅であろうと思うのだ。
芭蕉が許六との別れに臨み与えた言葉、と覚えているのだが。
「古人の跡をもとめず 古人の求たる所を もとめよ」
これは、もとは空海が言ったことという、有名な句である。
空海から発して芭蕉が許六に渡す、それを後世、胸にたたむ。
奥の細道をたどる旅、として芭蕉の名作『奥の細道』で芭蕉が実際に歩き辿った道筋をたどり歩く人々があとを絶たない。
たまたま、ここは最上川だなあと、川べりに佇み芭蕉の句、蕪村の句を思うことはあったが、道筋をなぞり歩くことを思いついたことはない。
梅雨どきである、庭石が濡れて潤いのある輝きを見せている朝。
紀行『笈の小文』を開きます。和歌山の紀三井寺のあたりで、旅の心を語っている、
「猶栖をさりて器物のねがひなし。空手なれば途中の愁もなし。寛歩駕にかへ、晩食肉よりも甘し。とまるべき道にかぎりなく、立べき朝に時なし。只一日のねがひ二つのみ。こよひ能宿からん、草鞋のわが足によろしきを求めんと計は、いさ丶かのおもひなり。時々気を転じ、日々に情をあらたむ。もしわずかに風雅ある人に出合たる、悦かぎりなし。日比は古めかしく、かたくななりと悪み捨たる程の人も、邊土の道づれにかたりあひ、はにふ・むぐらのうちにて見出したるなど、瓦石のうちに玉を拾ひ、泥中に金を得たる心地して、物にも書付、人にもかたらんとおもふぞ、又是旅のひとつなりかし」
生涯寓居の庇を借り、車を降りてのちは寛歩に頼り、とまるべき道にかぎりなく、立べき朝に時なし。これが今のありさま故、芭蕉の心が身に染み渡る。外目には一所に居着き暮らすかに映ろうとも心は片雲に漂う。旅の喜びの極めつけは、芭蕉さまが言われる通り、辺土のうちに語り合い、瓦石のうちに玉を拾う心地するところにあり、のちのち幾たびも思い出す宝である。
夢を、抱えている。頼る寛歩も不如意となるだろう、いつかの暁に、小さな葎姿の図書室を作り、誰となく入り来たり出でゆく道すがらの淀みのうたかたとすることだ、玉を得たる心地を味わう縁となるやも知れぬ。わが身は動けずとも、これも旅であろうと思うのだ。