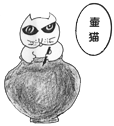浦島草
08-05-18 22:44
今年も浦島草の花が咲いた。手のひらの一回りも大きな葉を一枚だけ広げて、その下に咲く花は茶紫色の筒型で「大型の仏炎苞に包まれた肉穂花序」という表現をするが、これでは、何のことやらわからない。これはサトイモ科の植物で、同じくサトイモ科の水芭蕉とよく似た花の形、といったほうがわかるかもしれない。ラッパ状に上を向いた筒の先が細く長い糸のように伸びている、これが浦島太郎の持っていた釣竿の釣り糸に例えられて、浦島の名前をもらっている。
花屋さんで売られている花ではない、私は貰ったのでもなく、買ったのでもない、庭に自然に生えていたので見守っている。秋に朱色の実をつけるが、これはトウモロコシのような実のつき方をする。全く実のつかない年もある。
この植物の持つ特徴は、性転換をすることだ。小さいときにオスでいて、大きくなってくるとメスに変わったりする。無性のこともあるというが、眺めても私の目では判然としない。
もう一つの特徴は、ちょっとひどいなあ、と思うようなものだ。メスの花が受精しようという段になる、そこへオスの花の花粉をいっぱいつけた虫、虫はキノコバエというハエなのだが、これが飛んできて筒型のメス花の中に入り、受精が完了する。
さあ、めでたしめでたしで終わると思うでしょう。ところがキノコバエは花から出られずに死んでしまうのだ。入ったら最後、出られない仕組みになっている。私は、これはひどいなあと思う。出してあげたって良いではないか。閉じ込めてしまう理由を想像するに、トウモロコシの実のようにたくさんの粒が結実する植物だから、念入りに虫が飛び回り受精させようとして軟禁するのではないだろうか。いや、軟禁というより命の限り励めということだ。想像を逞しくして行けば行くほど、恐怖、残酷のメスと言わざるをえない。
この実は地に散ると芽を出すが、丸2年後に発芽する。サトイモのように、親芋の周りに小芋がたくさんつくので、小芋を分けて増やす方が簡単だ。増えすぎてあっちにもこっちにも芽が出ているが、花が咲くまでに成長するには数年かかるように思う。
浦島草とそっくりの姿で釣り糸がない種類はマムシグサと呼ばれて、山道でよく見かける。マムシというよりもコブラが鎌首を持ち上げて、こっちを見つめているといった感じの花だ。これは猛烈な毒草で、里芋みたいだな、と芋を食べると死ぬこともある。
浦島草もマムシグサと同じサポニンという成分を持っていて、口に入れてみた人の話では、マムシグサのレベルではない激痛が口内いっぱいになるそうで、飲み込んだら死ぬに決まっているだろうが、呑み込める代物ではないそうだ。
花屋さんで売られている花ではない、私は貰ったのでもなく、買ったのでもない、庭に自然に生えていたので見守っている。秋に朱色の実をつけるが、これはトウモロコシのような実のつき方をする。全く実のつかない年もある。
この植物の持つ特徴は、性転換をすることだ。小さいときにオスでいて、大きくなってくるとメスに変わったりする。無性のこともあるというが、眺めても私の目では判然としない。
もう一つの特徴は、ちょっとひどいなあ、と思うようなものだ。メスの花が受精しようという段になる、そこへオスの花の花粉をいっぱいつけた虫、虫はキノコバエというハエなのだが、これが飛んできて筒型のメス花の中に入り、受精が完了する。
さあ、めでたしめでたしで終わると思うでしょう。ところがキノコバエは花から出られずに死んでしまうのだ。入ったら最後、出られない仕組みになっている。私は、これはひどいなあと思う。出してあげたって良いではないか。閉じ込めてしまう理由を想像するに、トウモロコシの実のようにたくさんの粒が結実する植物だから、念入りに虫が飛び回り受精させようとして軟禁するのではないだろうか。いや、軟禁というより命の限り励めということだ。想像を逞しくして行けば行くほど、恐怖、残酷のメスと言わざるをえない。
この実は地に散ると芽を出すが、丸2年後に発芽する。サトイモのように、親芋の周りに小芋がたくさんつくので、小芋を分けて増やす方が簡単だ。増えすぎてあっちにもこっちにも芽が出ているが、花が咲くまでに成長するには数年かかるように思う。
浦島草とそっくりの姿で釣り糸がない種類はマムシグサと呼ばれて、山道でよく見かける。マムシというよりもコブラが鎌首を持ち上げて、こっちを見つめているといった感じの花だ。これは猛烈な毒草で、里芋みたいだな、と芋を食べると死ぬこともある。
浦島草もマムシグサと同じサポニンという成分を持っていて、口に入れてみた人の話では、マムシグサのレベルではない激痛が口内いっぱいになるそうで、飲み込んだら死ぬに決まっているだろうが、呑み込める代物ではないそうだ。