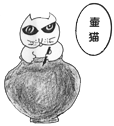富士猫の話 #5 嗅覚
18-01-15 15:23
猫については、毎日が発見である。私の場合は、土台に犬がいるので、すべてについて犬との比較になる。ご飯を食べさせるとき、富士が匂いに鈍感なことを発見した。トレイに3つの容器を置く。一つがドライフード、一つが缶詰や手作りの生もの、最後の一つは水の容れ物。「猫缶」が大好きで、缶を持つ私の手に頭をすり寄せてくる。はい、どうぞ。食べる事が生き甲斐みたいによく食べるが、ときどきトレイにこぼす。慌てるからですよ。ほら、ここに落としたわよ。
ここで犬と猫の違いが出る。千早だったら、こっちよ、なんて言われる前に見つけて食べてしまう。富士は、わからない。まるで見えないかのようだ。でも、あるある、と嗅ぎ回り、ほんの数㎝先の1㎝角の魚片を見つけるのに手間取る。犬と猫の嗅覚はレベルが違う。千早と野に出ているときに高鼻を嗅ぐ、取る、というが、風の匂いを取っていることがあり、その様子は自然と一体化していた。遠くの風上にいる獲物の存在を察知して調べている姿だ。
富士は室内猫だから気の毒だが、ハルターをつけて表に連れ出すと、草の先に鼻先を添わせて、調べるような仕草をすることがある。塀の角でも「調べて」いる。こんな様子を見ると、相当鼻が利くなあ、と思う。というのは、そのような仕草の時は、目を開いてはいても、ほとんど見ていないからだ。
富士は待ち伏せ方法の狩りをする猫族であり、千早は追跡方法で狩りをする犬族だと気がついて、これは改めて猫勉強の必要があると思ったのが、ネコ本漁りの発端だった。
嗅覚について分かったことは、犬より劣る嗅覚ではあるが、猫は、二つの嗅覚器官を持っているということだった。第二の嗅覚器官は鋤鼻器官(じょびきかん・VNO)といって、上顎の門歯のすぐ裏から鼻孔まで続く管があり、この管の中に化学受容体が入っている。この管は0.25mmという細さで、猫が自発的に筋肉を使って匂いを送り込むときにだけ機能する。富士がスズメノカタビラの細い葉の匂いを取るとき、上唇を上げて前歯をむきだし、口を半開きにする、これこそ鋤鼻器官を使っているのだった。そこには、富士が会ったことのない猫の匂いがあるのだ。ヒトにはできない業であります。こんな優れた嗅覚器官を持っているのに、どうしてトレイにこぼしたご飯を見つけるのに手間取るのだろう。それは見えていないからだった。なんで? と私は身を乗り出して先を読む。猫の視力は30㎝以内に焦点を合わせられない。こうしたことは、ネコ本を読まなかったら分からなかった大切なことで、ほらここよ、見えないの? バカねえ、などとくりかえしていたかもしれないのだ。
つきあう相手の能力を知ることが、つきあいの第一歩なのだった。特徴を知ること。努力ではできない、持たない能力を知ること。まだまだ発見は続きそうだ。
ここで犬と猫の違いが出る。千早だったら、こっちよ、なんて言われる前に見つけて食べてしまう。富士は、わからない。まるで見えないかのようだ。でも、あるある、と嗅ぎ回り、ほんの数㎝先の1㎝角の魚片を見つけるのに手間取る。犬と猫の嗅覚はレベルが違う。千早と野に出ているときに高鼻を嗅ぐ、取る、というが、風の匂いを取っていることがあり、その様子は自然と一体化していた。遠くの風上にいる獲物の存在を察知して調べている姿だ。
富士は室内猫だから気の毒だが、ハルターをつけて表に連れ出すと、草の先に鼻先を添わせて、調べるような仕草をすることがある。塀の角でも「調べて」いる。こんな様子を見ると、相当鼻が利くなあ、と思う。というのは、そのような仕草の時は、目を開いてはいても、ほとんど見ていないからだ。
富士は待ち伏せ方法の狩りをする猫族であり、千早は追跡方法で狩りをする犬族だと気がついて、これは改めて猫勉強の必要があると思ったのが、ネコ本漁りの発端だった。
嗅覚について分かったことは、犬より劣る嗅覚ではあるが、猫は、二つの嗅覚器官を持っているということだった。第二の嗅覚器官は鋤鼻器官(じょびきかん・VNO)といって、上顎の門歯のすぐ裏から鼻孔まで続く管があり、この管の中に化学受容体が入っている。この管は0.25mmという細さで、猫が自発的に筋肉を使って匂いを送り込むときにだけ機能する。富士がスズメノカタビラの細い葉の匂いを取るとき、上唇を上げて前歯をむきだし、口を半開きにする、これこそ鋤鼻器官を使っているのだった。そこには、富士が会ったことのない猫の匂いがあるのだ。ヒトにはできない業であります。こんな優れた嗅覚器官を持っているのに、どうしてトレイにこぼしたご飯を見つけるのに手間取るのだろう。それは見えていないからだった。なんで? と私は身を乗り出して先を読む。猫の視力は30㎝以内に焦点を合わせられない。こうしたことは、ネコ本を読まなかったら分からなかった大切なことで、ほらここよ、見えないの? バカねえ、などとくりかえしていたかもしれないのだ。
つきあう相手の能力を知ることが、つきあいの第一歩なのだった。特徴を知ること。努力ではできない、持たない能力を知ること。まだまだ発見は続きそうだ。