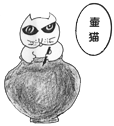吉川弘文館の案内 その2
22-07-20 09:53
吉川弘文館が『戦争孤児たちの戦後史』を今月刊行開始する。総集編・西日本編・東日本と満州編の全3巻。戦乱期の子供たちに視線が注がれるまでに、これだけの年月がかかった。このことに深い感慨を覚える。
ぜひ、手に取ってゆっくり読もうと思う。いったい何歳くらいの人々が携わり、出来上がったものだろう、そのことにも大きな関心がある。この3巻の中で取り上げられているだろう子供たちには、生きていたとしても表現する力はあまり残されてはいないはずだ、私の年代だからわかる。
当時、まがりなりにも屋根の下にいて家族が揃っており、乏しくとも口に入るものにありつけていた私は、上野の地下道にいるという孤児たちのことを思っていた、布団の中で寝ると思いだした、食べると思わずにいられなかった。しかし上野の地下道の孤児たちの情報は、口伝えでのみ、聞こえてくるニュースだった。新聞もラジオも触れなかった。ただ一つ、夕方始まるラジオドラマ『鐘の鳴る丘』が、父さん母さんいないけど〜 という明るく元気な歌声とともに戦災孤児たちの今を伝えようとしていた。その内容は、噂の内容とは別世界に感じられた。噂は、子供同士の噂ではない、大人たちが話し合っているのを、傍に立っていて見上げて聞いていた、そういう噂話だった。
神奈川県海老名市の海老名市立図書館の郷土資料の棚で、戦災孤児たちの記述に初めて出会った。が、それだけだった。数多の書き手が童話などの形で発表をしているが、姿勢を正し、真っ向から全体を把握しようとする動きは、これが初めてではないだろうか。立派な企画だと思う。戦争を知らない世代の人たちが手がけてくれるとしたら、それはさらに素晴らしいことだと思う。なぜかというと、過去を探索し、継承してゆく力を見ることができる故である。
ぜひ、手に取ってゆっくり読もうと思う。いったい何歳くらいの人々が携わり、出来上がったものだろう、そのことにも大きな関心がある。この3巻の中で取り上げられているだろう子供たちには、生きていたとしても表現する力はあまり残されてはいないはずだ、私の年代だからわかる。
当時、まがりなりにも屋根の下にいて家族が揃っており、乏しくとも口に入るものにありつけていた私は、上野の地下道にいるという孤児たちのことを思っていた、布団の中で寝ると思いだした、食べると思わずにいられなかった。しかし上野の地下道の孤児たちの情報は、口伝えでのみ、聞こえてくるニュースだった。新聞もラジオも触れなかった。ただ一つ、夕方始まるラジオドラマ『鐘の鳴る丘』が、父さん母さんいないけど〜 という明るく元気な歌声とともに戦災孤児たちの今を伝えようとしていた。その内容は、噂の内容とは別世界に感じられた。噂は、子供同士の噂ではない、大人たちが話し合っているのを、傍に立っていて見上げて聞いていた、そういう噂話だった。
神奈川県海老名市の海老名市立図書館の郷土資料の棚で、戦災孤児たちの記述に初めて出会った。が、それだけだった。数多の書き手が童話などの形で発表をしているが、姿勢を正し、真っ向から全体を把握しようとする動きは、これが初めてではないだろうか。立派な企画だと思う。戦争を知らない世代の人たちが手がけてくれるとしたら、それはさらに素晴らしいことだと思う。なぜかというと、過去を探索し、継承してゆく力を見ることができる故である。